組織は「平均的な人」を前提にしすぎていないか
どんな職場にも「組織になじみにくい」とされる社員がいます。
空気を読むのが苦手、同僚ができることを同じペースでこなせない、一般的なコミュニケーション様式に合わない──。こうした人材は往々にして「扱いにくい」とラベルづけされ、組織の同調圧力の中で浮き、やがて排除されていないでしょうか。私自身も排除する側だったとも思いますし、多くのクライアントでも話題に上がる話です。
しかし、本当にこれは「個人の問題」で通り過ぎて良いのかという不安があります。むしろ、組織側の設計が「平均的な人材」だけを想定していることに、問題の本質があるのではないでしょうか。
理論的視座:インクルーシブ組織論と人材活用
経営学・人材開発の分野では「インクルーシブ組織論」が注目されています。
これは「多様な特性を持つ人が排除されず、活躍できる環境をどうデザインするか」を問い直す考え方です。
たとえば勅使河原真衣氏らの研究は、組織における“異質性”が必ずしも負ではなく、適切な配置や役割調整によって、むしろ新しい視点や創造性をもたらすことを示しています。
現実的なアプローチ:排除ではなく“配置”で活かす
私自身の経験でも、組織になじみにくい社員が「力を発揮する瞬間」は確かに存在します。
重要なのは、その人を“平均”に近づけようと矯正するのではなく、以下のようなアプローチを取ることです。
- 役割・ジョブディスクリプションの再設計
全員に同じ役割を求めるのではなく、その人が比較的得意とする領域に寄せる。 - ポジティブな資質の明文化
組織で「この人は〇〇が得意だ」と共有することで、周囲も理解しやすくなる。 - チーム単位での補完関係を設計
「できないこと」を責めるのではなく、できることを軸に役割を補い合う。
適性検査の限界──“見極めツール”に頼りすぎない
最近では採用時に「適性検査」を導入する組織が増えています。確かに一定の指標は得られますが、それで「合う/合わない」を判定しすぎるのはリスクがあります。
人材は静的に測定できるものではなく、配置・関わり・組織文化によって「成功の確率」が変動するからです。
採用は五分五分のスタートラインにすぎず、成功か否かを決めるのは組織の側の設計です。
結論:インクルージョンは“余裕”ではなく“戦略”である
「組織になじみにくい社員」を排除するのは簡単です。しかし、それは短期的な“効率”を優先する発想にすぎません。
むしろ多様性を受け入れ、配置や役割を調整しながら力を引き出すことこそ、組織の持続的な成長につながります。
インクルージョンは「優しさ」や「余裕」ではなく、れっきとした経営戦略だと考えます。
を創る」シリーズ①-8-840x560.jpg)


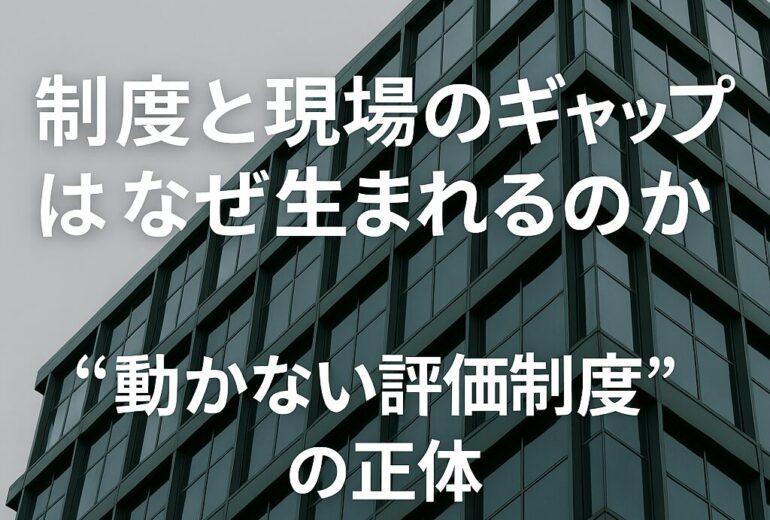
を創る」シリーズ①-19-770x520.jpg)
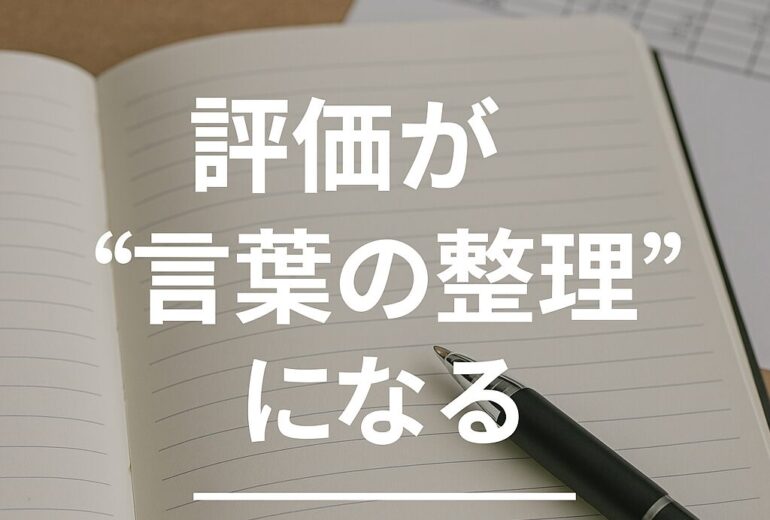

コメント