「学び直し」「リスキリング」とよく言われますが、
その前に必要なもの――それがアンラーン(unlearn)=学びほぐしです。
福祉現場でも、こんな言葉をよく聞きます。
- 「昔からこうしてきたから」
- 「今さら変えられない」
- 「それって意味あるの?」
これらは、学ばない“態度”のように見えますが、
実は多くの場合、これまでのやり方を手放すことへの不安や恐れが根っこにあるのです。
■ アンラーンは「忘れる」ことではない
アンラーンという言葉は誤解されがちですが、
「過去のやり方を否定してゼロに戻すこと」ではありません。
むしろ、
「これまでの経験に感謝しつつ、今の状況には合わない部分を“手放す”」
「やり方ではなく、“なぜそうしていたか”を問い直す」
といった**内省と対話を通じた“学びのほぐし”**のことを指します。
■ なぜアンラーンは難しいのか?
以下の3つの壁が、アンラーンの大きな障害になります。
- “正解”として身につけてしまっている
→ 成果を出した経験ほど、手放すのが怖くなる。 - アイデンティティと結びついている
→ やり方を変えることが、自分の価値の否定に感じられる。 - “新しいやり方”に自信がない
→ 手放したあとにどうすればよいか、見通しがない。
■ アンラーンを促すには、“揺らぎ”と“安全”の両方が必要
メッツァーロの変容的学習においても、
「方向喪失的ジレンマ」=これまでの考え方が通用しないと気づく瞬間が、アンラーンのきっかけになります。
ただし、ただ「揺さぶればよい」わけではありません。
- 「問い直す場」があり
- 「共に考える仲間」がいて
- 「失敗してもOKな空気」がある
こうした“安全な揺らぎ”を設計することが、アンラーンの起点になるのです。
■ 組織でできる具体策
① “問い直しの対話”を制度化する
例:定例会議で「そのやり方はなぜそうしているのか?」を問い直す時間を設け、仕組み化する
② 「過去の成功」を共有する
→ 今のやり方が生まれた背景を振り返ることで、手放すことへの納得を得やすくする。今のやり方も、更にその前の慣習を変革して始まっていたりします。その歴史を振り返ることで、更新が必要であることを自覚します。
③ “変化した先輩”のストーリーを可視化する
→ ベテランがやり方を変えた事例を共有することで「やっても大丈夫」というモデルが生まれる
④ アンラーンが起きた瞬間を称える
→ 成果ではなく、「やり方を見直したこと」自体を評価・称賛する文化づくり
■ まとめ:アンラーンとは「強い人」がするのではなく、「支えられた人」ができること
人は、自分の考えを疑うことに最も強い不安を抱きます。
だからこそ、アンラーンは組織ぐるみの取り組みである必要があります。
「自分のやり方を手放すことは、間違っていたということじゃない」
「次の一歩を、一緒に探していいんだ」
そう思える空気が広がって初めて、本当の意味で学びが始まるのです。
を創る」シリーズ①-1-840x560.jpg)


を創る」シリーズ①-1-1-770x520.jpg)
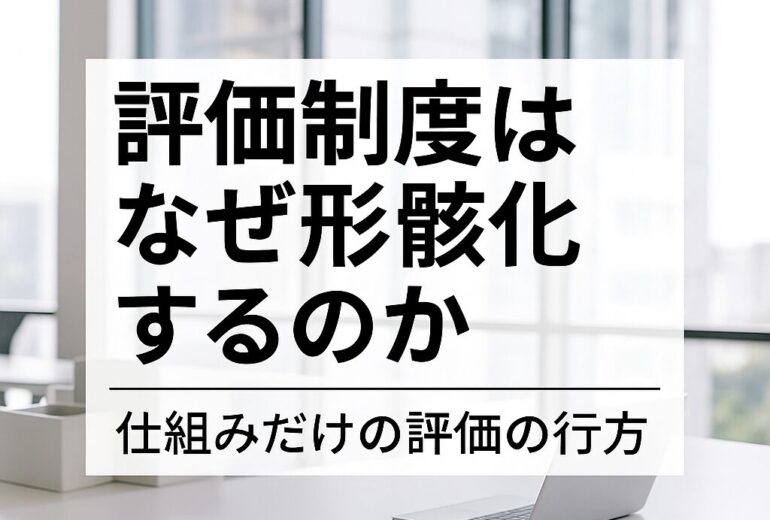
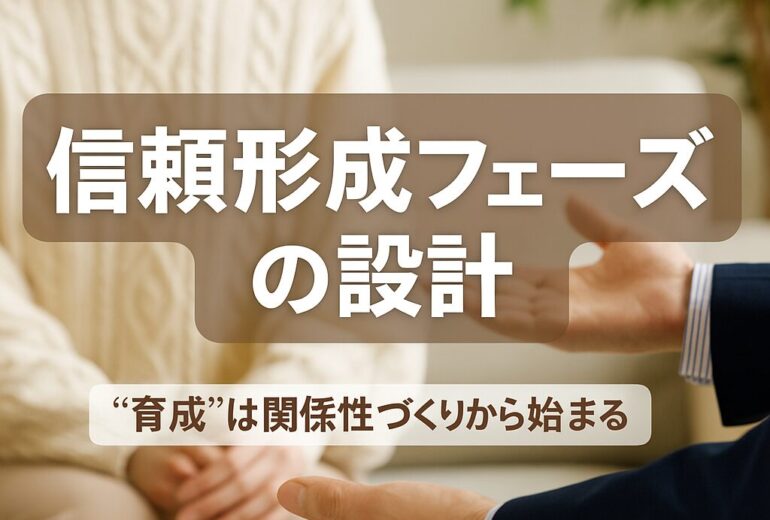
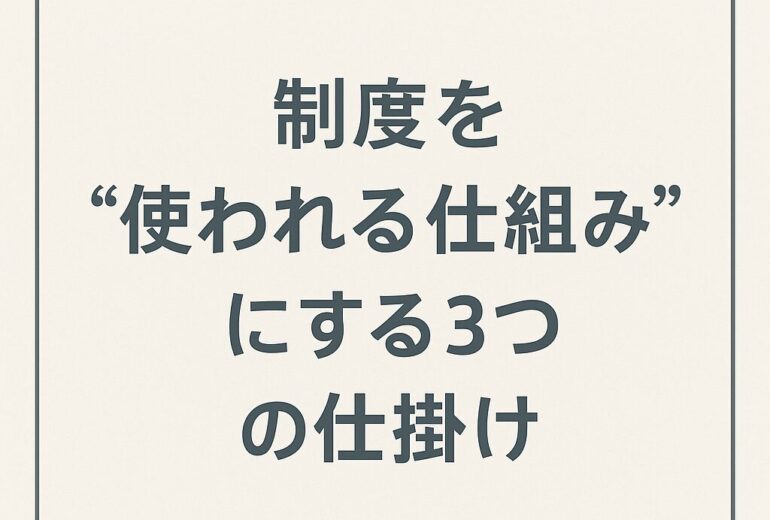
コメント