「なぜ若手は“やる気がない”と言われるのか?」
――世代間ギャップの前に、“期待のすれ違い”を見つめてみる
「今の若い職員は主体性がない」「指示待ちばかりで、こっちが疲れる」
福祉現場で経営者・管理職の方から、こうした声を聞く機会は少なくありません。
でも、若手本人に話を聞くと、実はまったく違う景色が見えてきます。
「ちゃんと考えて動こうとしている」「でも意見を言ったら否定される」
「いきなりハードルの高い責任を背負わされた」――そんな本音がそこにはあります。
■ ギャップの正体は「立場の違い」ではない
私たちはつい、“世代”のせいにしたくなります。
でも、問題の本質は、「見ているもの」「感じているもの」が違うことです。
- 経営層や管理職は「人手不足」「責任の重さ」「継続性への不安」を背負っている
- 一方、若手職員は「経験不足」「人間関係への不安」「意見を聞いてもらえない葛藤」を抱えている
これは、どちらが正しい・間違っているという話ではありません。
両者が“違う立場”から、違う視点で組織を見ているだけです。経営層は若手に不安を持ち、若手は経営層・管理職に不安を持っています。
■ スーパーのキャリア発達理論から見る“期待のズレ”
キャリア心理学者ドナルド・スーパーは、人生を通じたキャリアの発達段階を提示しました。
- 若手職員は「試行期・確立期」にいて、まだ自信も確信もありません
- 経営層やベテラン職員は「維持期・円熟期」にいて、安定性や責任に重きを置きます
この違いが、“なぜ主体的に動かないのか?”というすれ違いの原因でもあります。
若手が「やる気がない」のではなく、「怖くて動けない」のです。
■ 若手の声に耳を傾けることは、“評価”ではなく“共創”のスタート
若手の声を聞く――この行為が「評価の対象」になる組織も少なくありません。
「そんなことを言う前に、まずはやることやってから言えよ」
これは、せっかく芽生えた対話の芽を摘んでしまいます。直接的に言葉で言ってはいなくても、表情やボディランゲージでも伝わってしまいます。
本当に必要なのは、「経営層もまだ学びの途中である」と示す姿勢ではないでしょうか。
完璧な答えを持つのではなく、「一緒に考えたい」という態度を見せること。
それが、信頼の土台をつくっていく第一歩です。
■ 次回予告
次回は、なぜ「経営層の学び」が必要なのかを深掘りしていきます。
若手とのギャップの根っこにある「組織の学びの断絶」について、整理してみましょう。
✒️Live alive株式会社では、福祉法人向けに「世代間ギャップの可視化」や「若手職員との対話設計」「経営層向けの学び直しプログラム」などの支援も行っています。
お気軽にご相談ください。
を創る」シリーズ①-3-840x560.jpg)
を創る」シリーズ①-6-770x520.jpg)
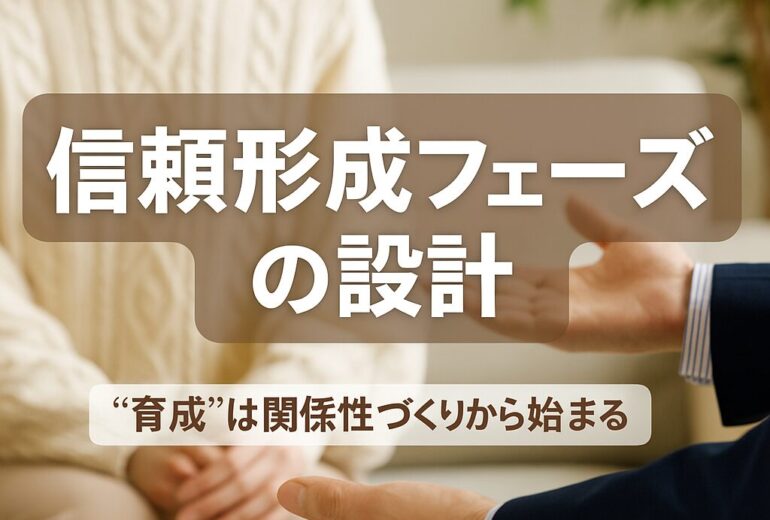
を創る」シリーズ①-19-770x520.jpg)
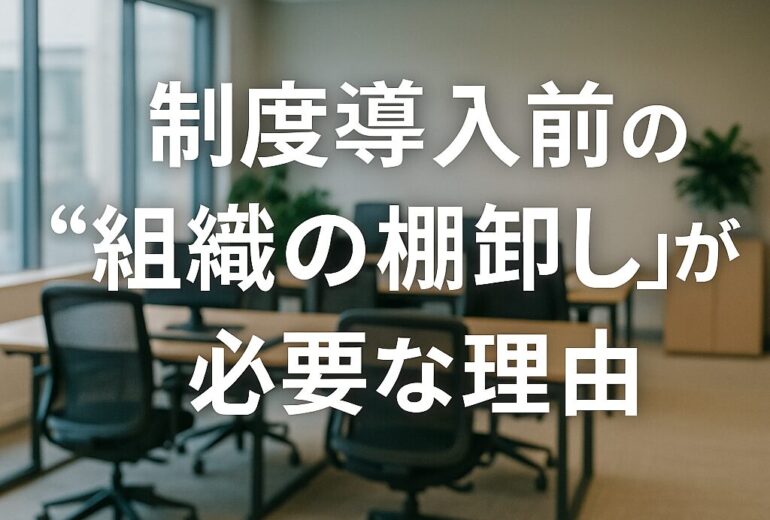

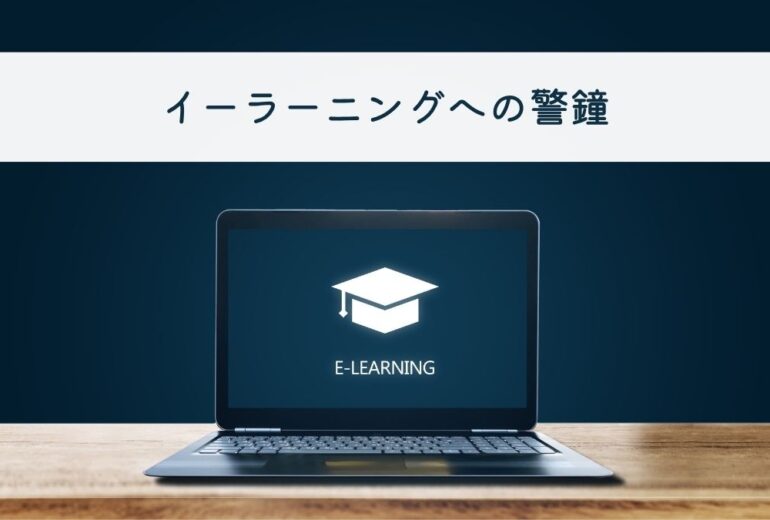
コメント