① 導入|評価制度の“心臓部”は面談
評価制度は導入したけど、「結局、誰がどう話すかが大事なんですよね…」
これは、制度導入を終えた法人の施設長が漏らした言葉です。
制度は整えた。でも、実際の面談はなんとなく。
毎月の1on1も、上司の負担になっていて、形式的な“確認の場”に終わっている。
評価制度がうまくいくかどうかは、「面談が機能しているか」で決まります。
② 問題提起|面談が“うまくいかない”福祉現場あるある
- 上司も忙しく、話す内容が浮かばない
- 毎回「最近どう?」のループ
- 部下も本音を言わず、建前だけ
- 面談の記録もされず、振り返りもされない
これでは、制度が「育成」や「定着」につながることはありません。
むしろ、評価=面倒、意味ない、やらされてる感が上司・部下側両方に残ってしまう。
③ 解決視点|“意味のある面談”を支える2つの工夫
1|面談は「雑談」で入っていい
面談は構えすぎないほうがうまくいく——
「最近どう?」という入り方でまったく問題ありません。
むしろ、“評価される”と思って緊張している職員にとっては、
こうした雑談的な始まりが、本音を話すための余白になります。
大事なのは、その会話の中から、今、その人が向き合っている“たった一つ”に焦点を当てること。
問いが変わると、対話の深さも変わります。
2|シングルフォーカスが面談の質を決める
福祉現場は多忙です。
あれもこれも…と目標を並べても、職員の頭にも、日々の実践にも残りません。
Live aliveでは、面談の中で「今月はこれに取り組もう」という1点集中の目標を一緒に言語化することを重視しています。
それが小さな改善であっても、「この1ヶ月、自分はこれを頑張った」と言えることが、
自己効力感と定着意欲につながります。
④ まとめ|面談は、制度と現場をつなぐ“細いけど強い糸”
評価制度は、用意するだけでは育成にはつながりません。
その制度を、日々の対話の中で意味づけし、焦点を当てていく面談こそが現場を変えます。
- 雑談から始めることで、緊張がゆるむ
- シンプルな目標で“次の一歩”が生まれる
- 上司と部下の対話が、職場に「信頼の文化」をつくる
そんな面談が月に1回あるだけで、
「この職場にいたい」「ちゃんと見てもらえている」という実感が職員に生まれていきます。

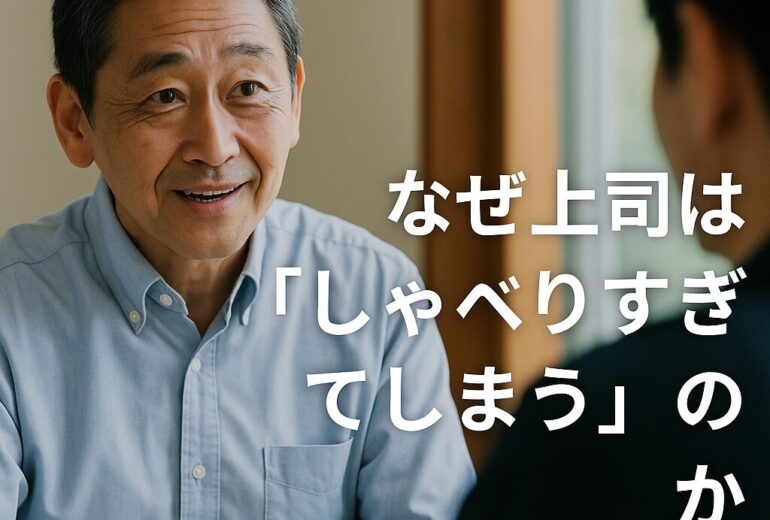
を創る」シリーズ①-19-770x520.jpg)
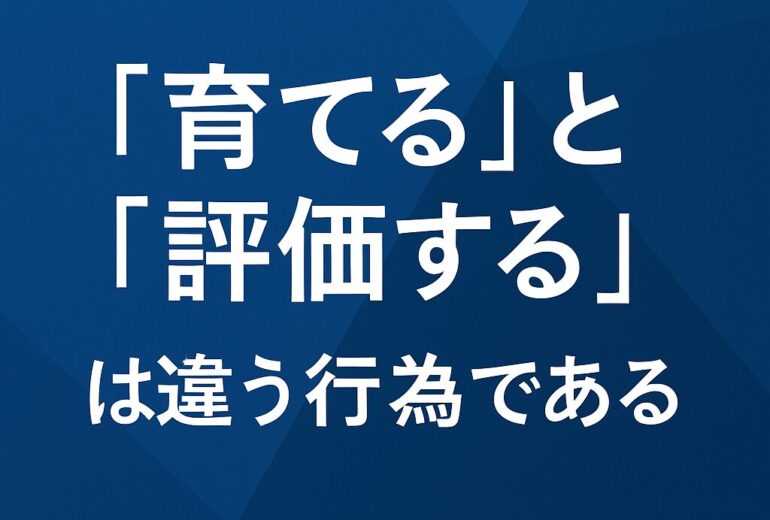
を創る」シリーズ①-1-770x520.jpg)
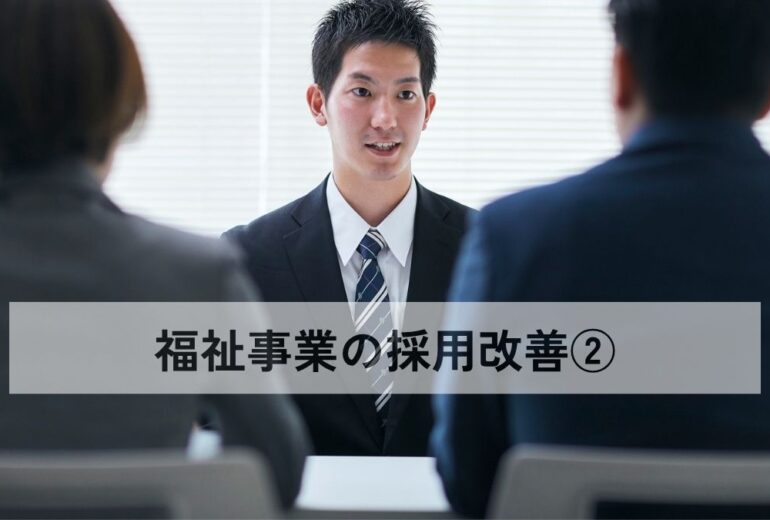

コメント