残念ですが、よく「採用ミスだったかもしれない・・・」という言葉を耳にします。限られた予算で、組織を良くしていくために選考の精度を上げようとすることは当然です。そして、そこにエネルギーをかけるほどに、入社後に活躍できない事象が起こると、管理職側で「採用ミス」という言葉が浮かぶのも理解できます。
しかし実際には、採用の成功/失敗を決めるのは候補者本人だけではなく、むしろ採用後に組織側がどのように“迎え入れるか”にかかっていると考えています。
つまり、「誰を採用したか」で勝負が決まるのではなく、採用した人材をいかに定着させ、活躍につなげるかという組織側の力が問われているのです。
オンボーディングの3類型
尾形真実哉氏の著書『組織になじませる力』(英治出版)では、オンボーディングを以下の3つに整理しています(引用元:同書)。
- タスク型:業務遂行に必要な知識やスキルを早期に習得させる
- リレーション型:人間関係を築き、相談先や協力者を確保する
- カルチャー型:組織の価値観や行動規範を浸透させる
多くの企業はタスク型に偏りがちですが、リレーション型やカルチャー型が欠けると早期離職の温床になると指摘されています。
採用を「成功」に変えるのは組織
採用した人材を「ミスマッチ」と決めつけるのは簡単です。
しかし、実際にはオンボーディングを通じて組織側がどれだけ“なじませる力”を発揮できるかが成功の分かれ目となります。
- 早期離職を防ぐには、配属直後からのフォローが不可欠。
- 定着率を高めるには、人事制度や評価制度と同様にオンボーディング設計を組織戦略に組み込むことが重要です。
経営者に求められる視点
「採用はゴール」ではなく「採用はスタート」でしかないと考えます。採用をゴールだと思うほどに、入社後に”減点主義”になりがちです。
新しい人材が組織に根付き、成果を出すまでのプロセスを整備することこそ、人材投資のリターンを最大化する鍵になります。
経営者が“定着率の経済学”を理解すると同時に、“オンボーディングの科学”に基づいた仕組みを構築することが、離職防止と成長の両立を可能にします。
を創る」シリーズ①-6-840x560.jpg)
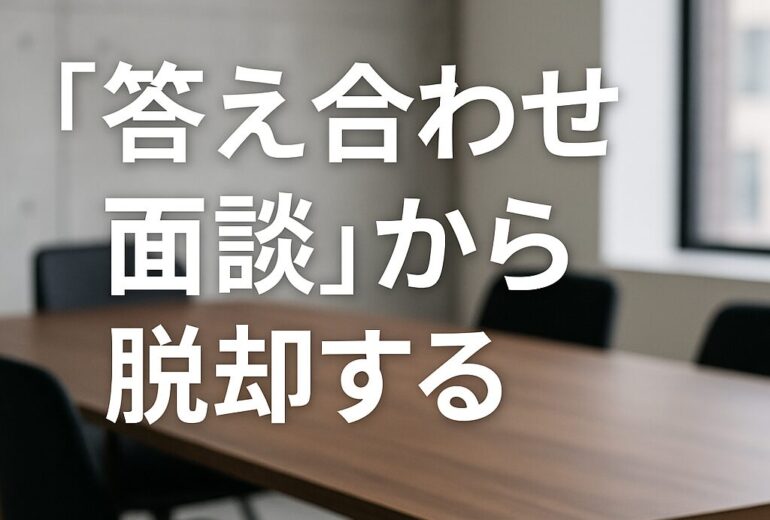
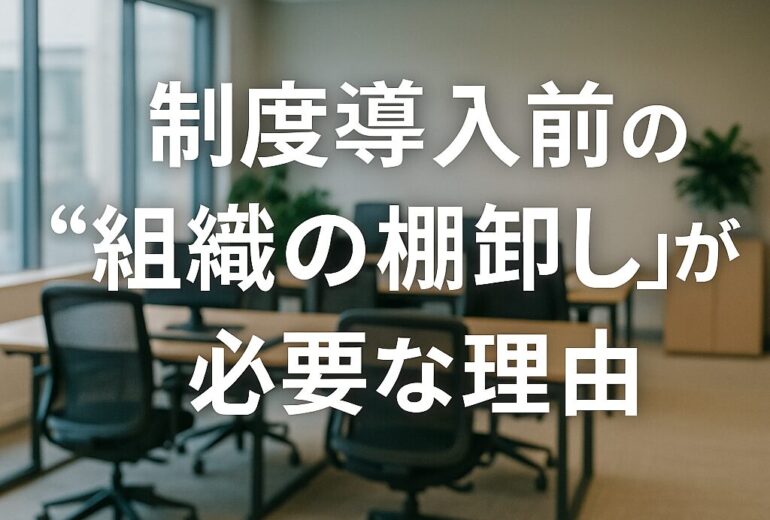

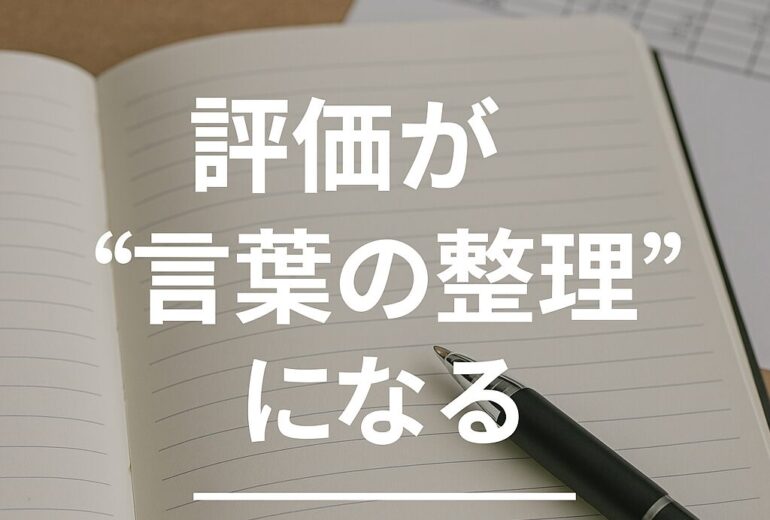
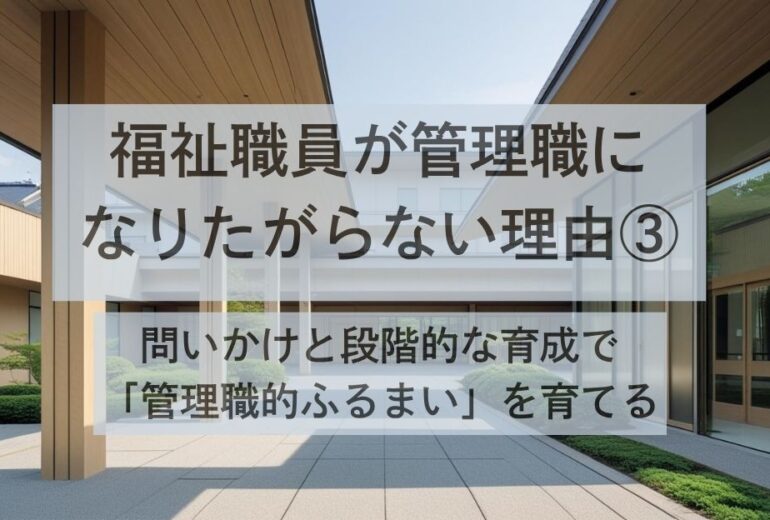
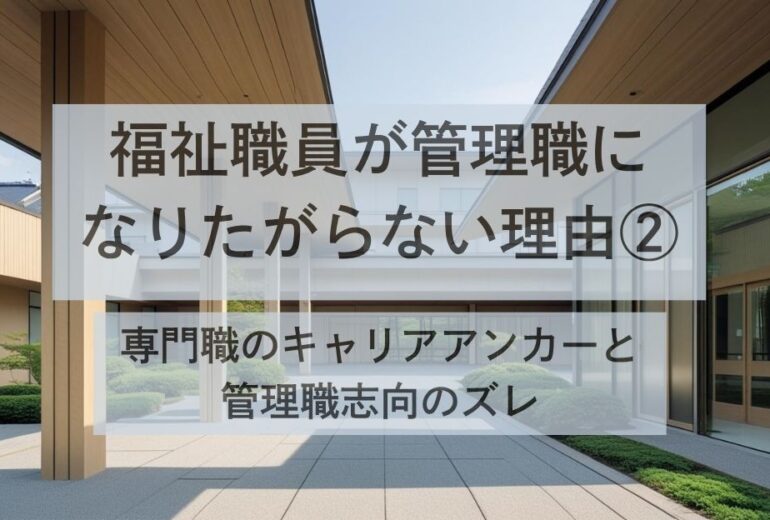
コメント