福祉の現場では「クセがない人が欲しい」「平均的にできる人なら安心」といった声をよく耳にします。
しかし実際には、誰もが得意・不得意の凸凹を持っています。
「バランスが取れた完璧な人材」など存在しないのです。
にもかかわらず、組織は「みんな同じようにできること」を暗黙に期待しがちです。
そして、その基準から外れると「扱いにくい人」と見なしてしまいます。
では、本当に人を活かす方法は何なのかを考え続けています。
適性検査などに頼りすぎるリスク
近年、適性検査や各種アセスメントツールが普及しています。
もちろん、採用や配置の参考にはなります。
しかし、それだけで「合う・合わない」を決めつけてしまうと、本来発揮できる力を見落とす危険があります。
人材の能力や適性は、職務内容や職場環境との相互作用で変化します。
つまり、採用時点で成功か失敗かが決まるのではなく、入社後の配置や役割調整次第で花開きます。
適性検査で自組織との相性が良いという結果が出た人も、そうでない人も、入社後に活躍するかどうかは採用時点では五分五分なのだと考えています。
配置と役割再設計がカギ
ここで重要になるのが「ジョブクラフティング」の考え方です。
これは、職員自身や上司が、強みや関心に基づいて「仕事の進め方・人間関係・捉え方」を再設計するという発想です。
例えば──
- ケア・支援記録が苦手でも、子どもや利用者さんとの対話で信頼を築く力がある人
- ICTが得意で、現場の業務改善をリードできる人
- 地域との関係構築が得意で、法人の外部活動に大きく貢献できる人
こうした凸凹を活かす配置や役割の再設計をすれば、「戦力外」と思われていた人が「欠かせない存在」に変わります。
福祉現場での実践
福祉業界では「誰もが同じケアを提供できる」ことを理想に掲げがちですが、これは幻想に近い部分もあります。
標準化は必要ですが、それと同時に人材の凸凹を組織の資源として活かす視点が欠かせません。
現場でできる実践例:
- 定期的な1on1で「得意・不得意」を言語化する
- チーム内で「この人の強みはこれ」という共有リストをつくる
- 目標(MBOやOKR)はチーム内でオープンにしておく
- 評価制度を「弱点の矯正」から「強みの発揮度」にシフトする
まとめ
「普通の人」「クセのない人」など存在しません。
存在するのは、それぞれが持つ凸凹と、その活かし方を考える組織の工夫です。
適性検査に頼りきるのではなく、配置・役割の再設計を科学的に進めること。
それこそが、福祉現場で人を活かし、組織を強くする最大のポイントです。
を創る」シリーズ①-11-840x560.jpg)
を創る」シリーズ①-4-770x520.jpg)
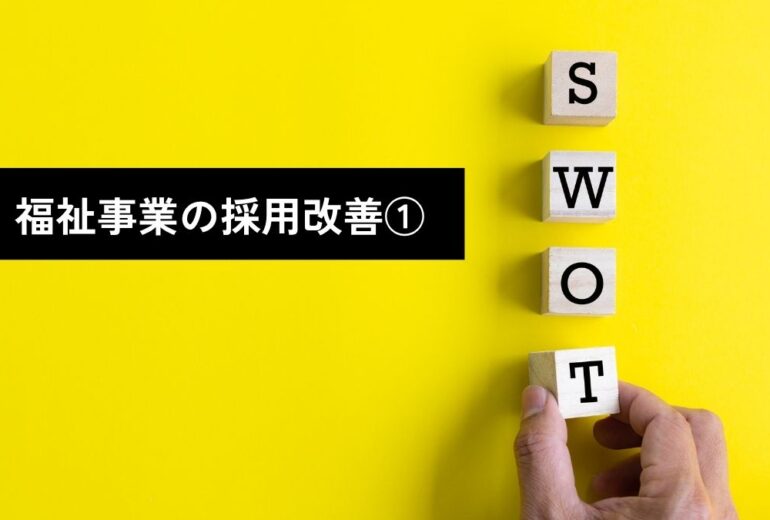
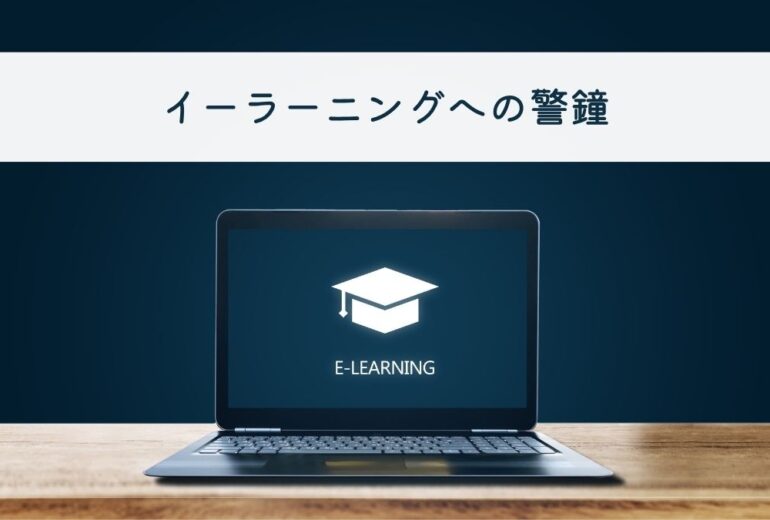

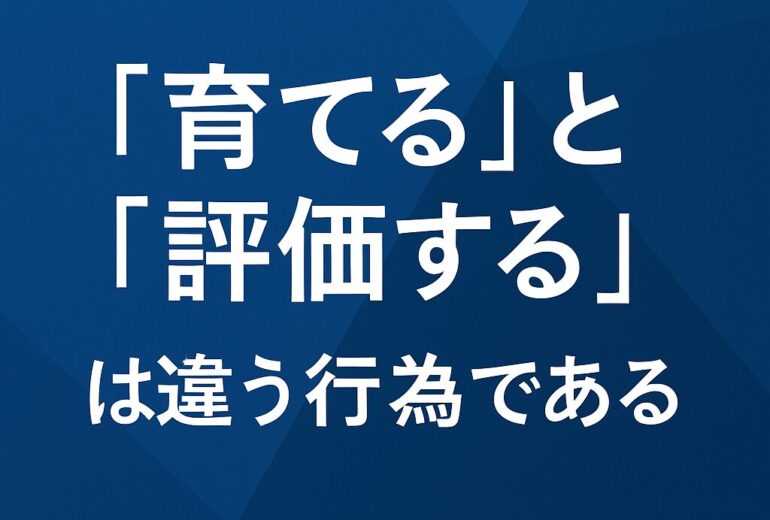
を創る」シリーズ①-3-1-770x520.jpg)
コメント