――“文化としての学び”を育てる、経営の責任
このシリーズでは、以下のような視点から「学び続ける組織」について考えてきました:
- 「学べ」と言われても、仕組みがなければ続かない
- トップが学ぶ姿を見せることで、組織に学びが根づく
- 学びは“贅沢”ではなく、“変化の痛み”から生まれる
- 心理的安全性がなければ、学びは習慣にならない
- 新たな学びの前に、まずアンラーン(学びほぐし)が必要
そして今回の最終回では、これらすべてを支える土台――
**「学びが“文化”になるために、経営は何をすべきか?」**を整理します。
■ “制度”だけでは、学びは定着しない
多くの法人が研修制度を整え、eラーニングを導入し、評価項目にも「学び」や「成長」を組み込もうとしています。
これは素晴らしい取り組みです。
しかし一方で、現場からはこうした声も聞こえます:
- 「研修に出ても、現場で共有されない」
- 「上司がそもそも学んでいない」
- 「忙しさに押し流されて終わる」
これはつまり、「制度があっても“空気”がない」状態です。
■ 学びを支える“空気”とは何か?
制度や仕組みが“枠組み”だとすれば、
空気(文化)はその中で息づく“日常の関係性”や“感情の流れ”です。
たとえば、こんなやりとりがあるかどうか。
- 「この前の研修、どうだった?」と自然に声がかかる
- 「やってみたけど、どうもうまくいかなくて」と失敗も共有される
- 「いいね、それ真似させて」と称賛や模倣が飛び交う
これは制度ではなく、日々のふるまいと関係性によってつくられるもの。
そしてこの“空気”こそが、学びが根づくか否かを決める最大の要素なのです。
■ 経営が変えるべきは「問いかけ」と「姿勢」
学ぶ組織において、経営者の仕事は“指示すること”ではありません。
むしろ、問い続けることです。
- 「最近、何にモヤモヤしていますか?」
- 「これは現場の声をどう反映させていますか?」
- 「自分たちのやり方は、本当に最善ですか?」
こうした問いを自ら投げ、
同時に、自分自身が学ぶ姿勢を見せることが文化を変えるスタートです。
■ 「学びたくなる風景」をつくる
結局、学びは“空気感染”します。
- ベテランが若手に教えを乞う
- 経営者が勉強会の輪の中にいる
- 管理職が「私、これわかってなくて」と言う
そんな風景が、職員にとっての「普通」になることが、
どんな制度よりも強く、学びを文化にしていきます。
■ 学ぶ組織とは、「学ぶことが気まずくない組織」
私たちが目指すべきなのは、「学ぶ人を評価する組織」ではありません。
そうではなく、
「学ぶことが当たり前であり、むしろ“学ばない”ことの方が不自然に感じられる」
という組織風土です。
それは、制度ではなく人と人との関係性からしか生まれません。
■ 経営に問いたい:
あなた自身は、最近、何を学びましたか?
これはきっと、現場の職員に「学びましょう」と言うよりも、ずっと強いメッセージになります。
✒️Live alive株式会社では、
制度設計から文化づくりまで、学びが根づく法人運営を一緒に考えています。
を創る」シリーズ①-2-840x560.jpg)
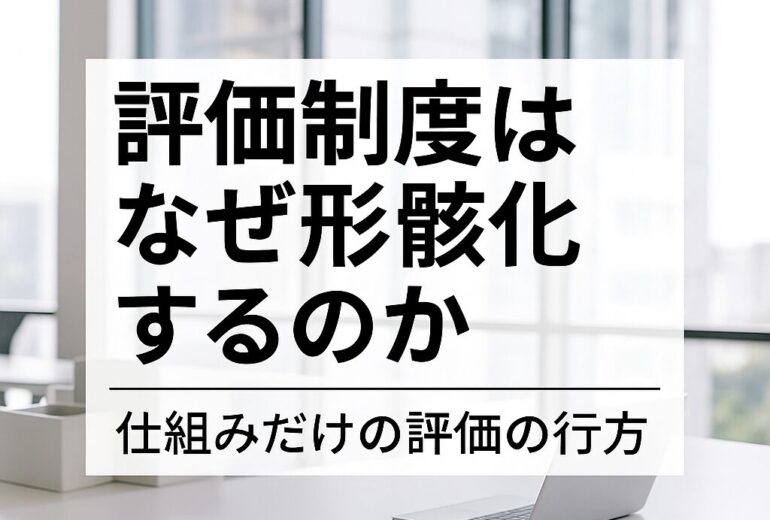
を創る」シリーズ①-12-770x520.jpg)
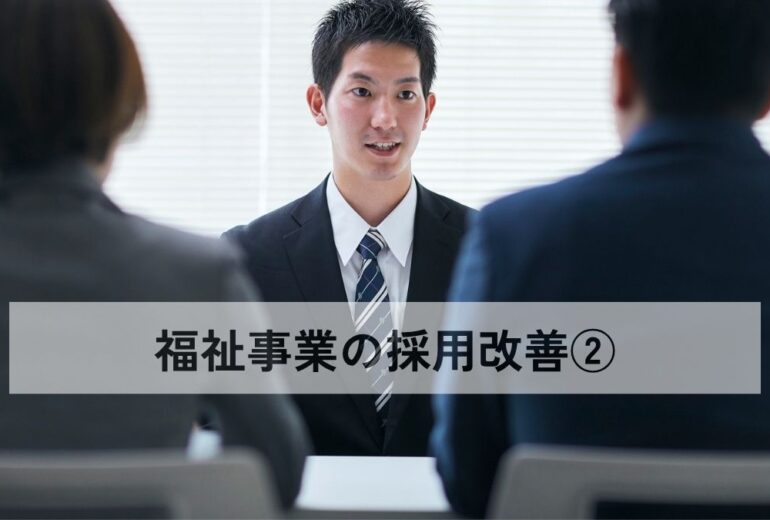
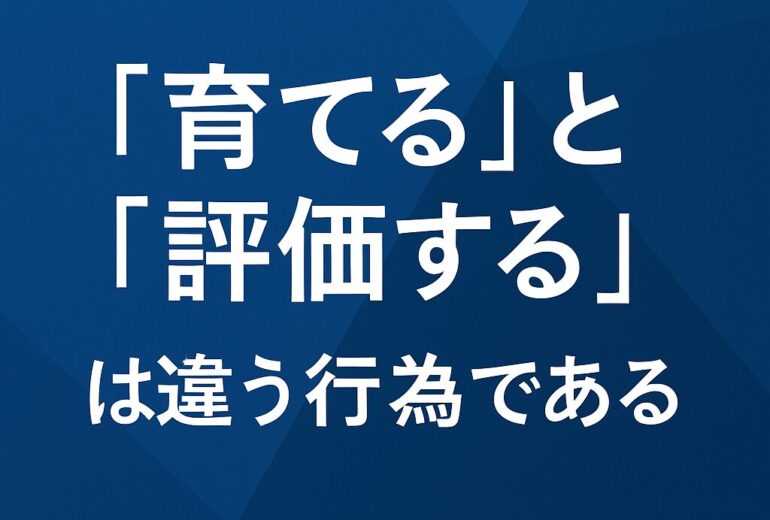
を創る」シリーズ①-19-770x520.jpg)
を創る」シリーズ①-1-1-770x520.jpg)
コメント