――一人の努力ではなく、仕組みとして学びを育てる
「学び続けることが大切」
福祉業界でもそうした言葉を耳にする機会が増えてきました。
経営層や研修担当者の中には、「職員にはもっと自己研鑽してほしい」と願う方も多いでしょう。
でも現場では、こんな声が聞こえてきます。
- 「勉強しても現場では活かせない」
- 「学びを共有する文化がない」
- 「結局、学ぶ人と学ばない人に分かれる」
これらはすべて、“学びを個人に委ねている組織”で起こる問題です。
本当に必要なのは、組織として“学びを支える仕組み”をつくることです。
■ “学べ”と言うだけでは、学びは続かない
よくあるのが、「研修には出たけど、学んだ内容はその場限り」というケース。
職員が悪いのではなく、学んだことを実践し、対話し、問い直す土壌がないのです。
組織に仕組みがなければ、学びは“個人の努力”で終わってしまいます。
それでは、学ぶ人ほど孤立し、モチベーションを失っていきます。
■ 学びを支える“仕組み”とは?
以下のような仕組みは、学びを文化として根づかせる上で有効です。
- ピアラーニング(同僚学習):学びを共有する仲間がいるか
- 1on1の対話:学びを振り返る機会があるか
- 越境学習:組織外から刺激を受ける場があるか
- ナレッジマネジメント:学んだ知識が蓄積・可視化されているか
これらは「制度」ではなく「習慣」に近いものです。
日常の中で自然に行われてこそ、“学ぶ組織”は動き出します。
■ 「分からない」と言える組織であるか?
「心理的安全性」は、学びの土台です。
年齢・役職にかかわらず、「分からない」「学びたい」「教えてほしい」と言える風土がなければ、誰もチャレンジしようとは思いません。
その意味で、“分からないことが言える組織”は、学び続ける組織なのです。私たちは、分からないことが言える組織は、”上司が常に「分からない」「教えて」と言い続けている組織”だと考えています。上司こそが常に外部の新しい知見に触れ、”自分たちには、分からないことがまだまだたくさんある”ことを自覚し、そう宣言している組織なのではないでしょうか。
■ 学びは、行動・対話・問いの中で深まる
学びの本質は、「知ること」よりも「変わること」にあります。
- 学んだことを現場でやってみる
- 同僚や上司と語り合う・振り返る
- 新たな問いを持ち、また学びに向かう
このサイクルが、学びを一過性ではなく「文化」に変えていきます。
■ トップが学びの旗を振る組織は、自然に動き出す
現場職員にだけ学びを求める組織と、
トップ自らが「学びの最前線にいる」組織では、空気がまったく違います。
経営層・管理職が問いを持ち、変化し続ける姿を見せることで、
「この組織では、年齢や役職に関係なく学べるんだ」というメッセージが伝わります。
■ 次回予告
次回は、ベテランや経営層が「なぜ学びにくくなるのか?」
その心理的な壁と、それを超える方法について掘り下げていきます。
を創る」シリーズ①-840x560.jpg)
を創る」シリーズ①-6-770x520.jpg)
を創る」シリーズ①-8-770x520.jpg)
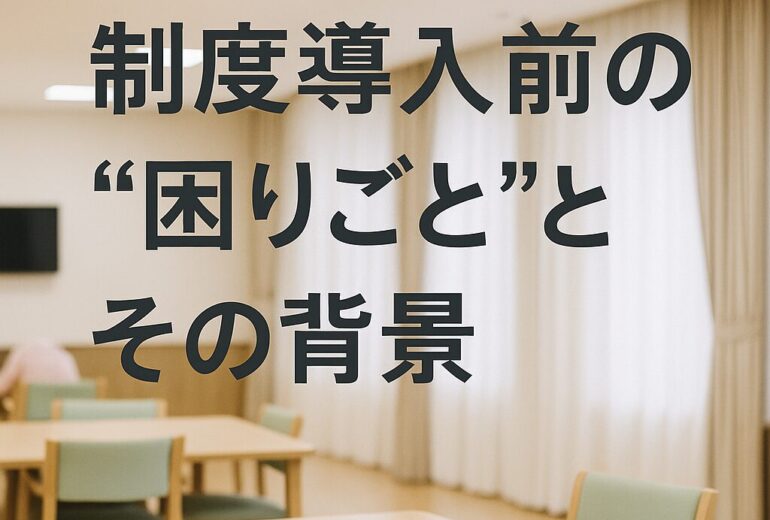
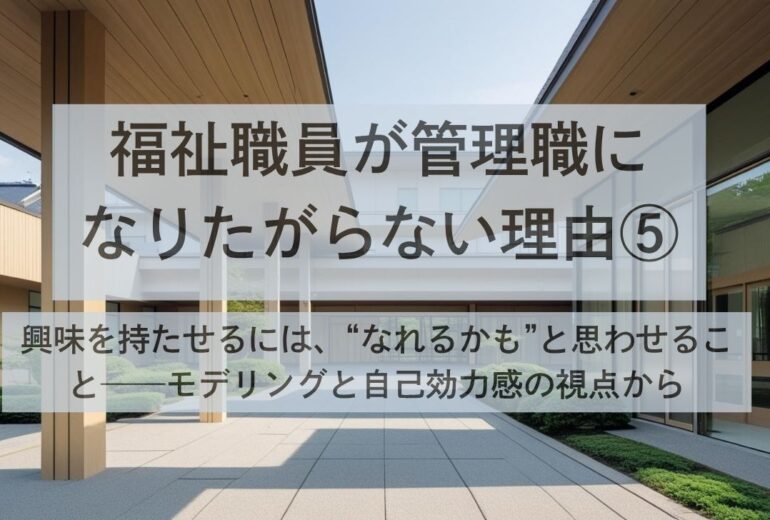
を創る」シリーズ①-2-1-770x520.jpg)

コメント