――中高年が“学びのトップランナー”になるために必要なこと
最近では、リスキリング(学び直し)やアンラーン(学びほぐし)という言葉が、福祉業界でも広く語られるようになりました。
研修を受けたり、読書をしたり、SNSで発信する中高年職員の姿も増えています。
これは素晴らしい変化ですし、組織にとって大きな財産です。
ただ、その一方で、こう思うこともありませんか?
「学んでいるはずなのに、なぜか現場の空気は変わらない」
「新しいことを知っているのに、行動は変わっていない」
■ リスキリングは“アイデンティティ”に触れる学びである
本気のリスキリングとは、単に新しいスキルを身につけることではありません。
それまでの「自分らしさ」「やり方」「プライド」に向き合い、
ときに“これまでの自分”を揺るがすような問いを受け入れることです。
Live aliveは、こう考えています。
リスキリングとは、自分のアイデンティティが危機に陥るほどのショックの中でしか、本当の意味では起こらない。
■ “贅沢な学び”も、大切な第一歩
現状を大きく変えず、プラスアルファとして学ぼうとする人を否定するつもりはありません。
むしろそれは、忙しい業務の中で時間をつくり、「何か変わりたい」と願う強い意志の表れです。
その一歩一歩が、組織に新しい風を呼び込んでいます。
でも、それが本当の意味での変化につながっていないとしたら?
どこかで“痛みを伴う問い”と向き合う必要があるのかもしれません。
■ メッツァーロの変容的学習:揺らぎこそ、学びの扉
学習理論家ジャック・メッツァーロは、人が深く学び直すのは、
「方向喪失的ジレンマ(disorienting dilemma)」――つまり“揺らぎ”の中だと述べています。
- 「このやり方ではもう通用しない」
- 「若手の気持ちがわからない」
- 「新しい技術や考え方に遅れを感じる」
このような不安や違和感が、真のリスキリングの扉を開くのです。若手職員は毎日、”自分のアイデンティティ”を揺さぶられるような指摘を受けたり、常に学習をするように指摘を受けているにも関わらず、経営層・管理職・中高年社員は、自分の立場や”らしさ”はそのままに、プラスαの学びをするだけで良いのでしょうか?
■ 中高年が“学びのトップランナー”である組織は、未来をつくる
変わり続ける上司や経営層がいる職場には、自然と「自分も変わっていいんだ」という空気が広がります。
それが若手の挑戦意欲を引き出し、組織の柔軟性や信頼感にもつながります。
■ 次回予告
上記の問題提起を受けて、次回はどうやってアンラーンを行うことができるのか?ということを書いてみたいと思います。


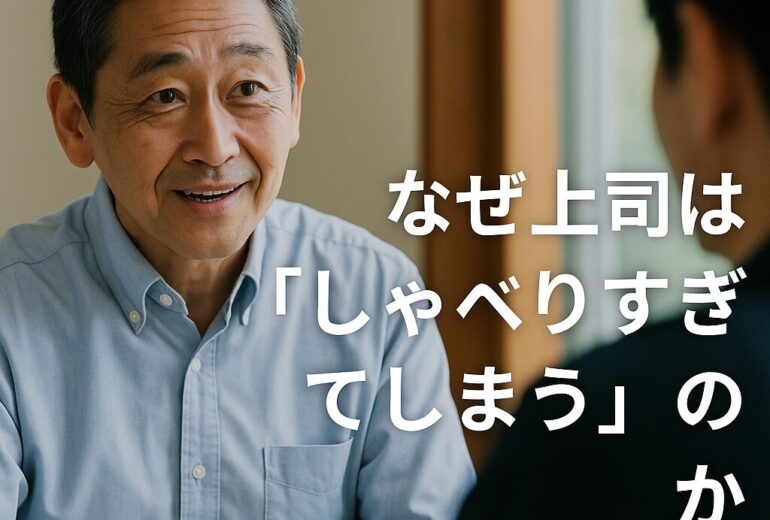
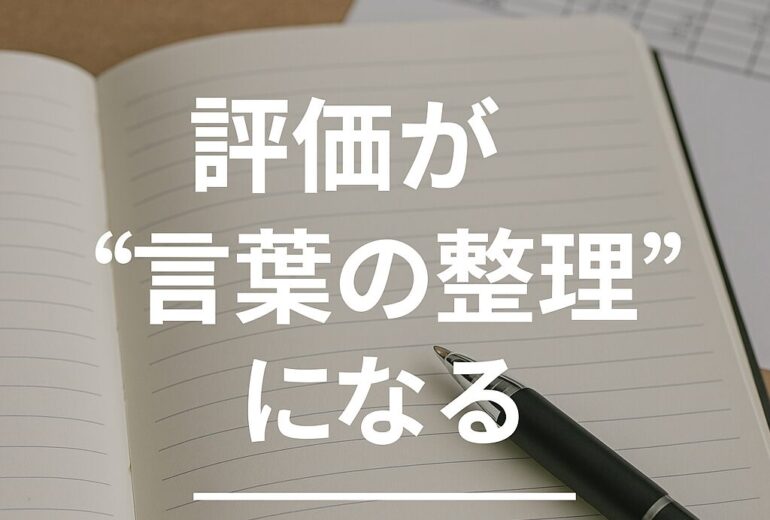
を創る」シリーズ①-1-770x520.jpg)
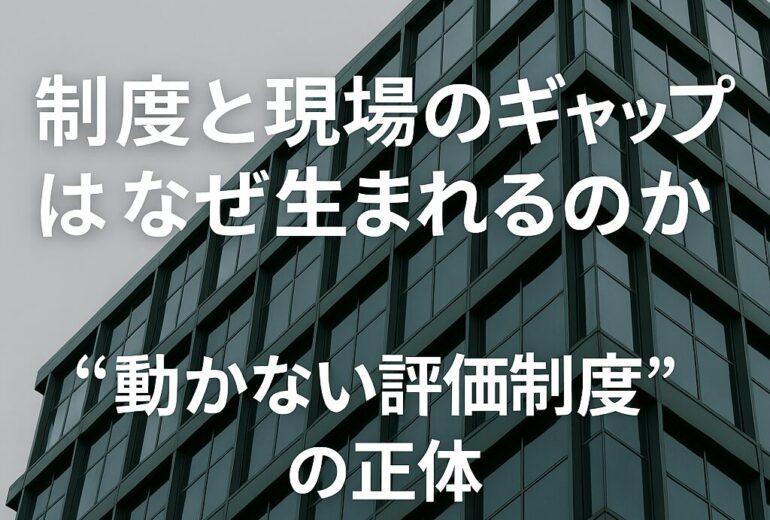
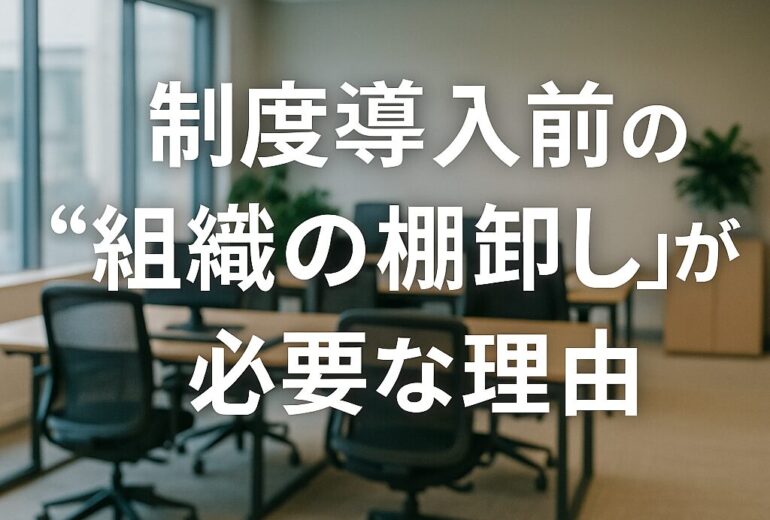
コメント