① 導入|「制度を作ったのに、うまくいかない」
ある法人の施設長や本部の方から、こんなご相談をいただくことが多いです。
「評価制度、作ったんです。でも“使われてない”んですよね…。
評価シートもある。運用フローもある。でも、職員は“なんのためにあるのか”ピンときていないし、自分自身もピンとこない。」
制度はあるのに、現場が動かない。
この「ギャップ」は多くの法人で起きています。
② 現場とのギャップは“導入プロセス”にある
制度が機能しない一番の理由。
それは、「制度が現場の言葉になっていない」からです。
- 経営層が制度を外注で導入
- スタッフは“知らないうちに評価されている”感覚
- 説明はあったけど、納得はなかった
- 日々の業務と制度がつながっていない
このような状態では、制度は“上から降ってきたもの”になります。
③ 現場と制度をつなぐ“3つの接着剤”
1|言葉を“現場のもの”に翻訳する
たとえば「主体性」「チーム貢献」――
よく使われる評価項目ですが、**現場ではどう見えるのか?**が共有されていないことが多い。
Live aliveでは、項目ごとに「行動レベルでの定義(例:こんな行動)」を整理し、
職員が「これは自分のことだ」と思えるように言葉を変換します。
2|制度の“使い方”まで設計する
制度の説明はした。でも“どのタイミングで誰がどう使うか”が不明確――これも多くのギャップ原因。
- 面談はいつ、どの頻度で?
- 誰が記録して、誰が見返すの?
- フィードバックはどう渡すの?
これらをあらかじめテンプレート化し、「迷わず使える設計」にする必要があります。
3|“制度を使って育つ”場をつくる
制度が定着するのは、「制度を通じて前向きな経験」ができたときです。
- 面談で「見てもらえている」と感じた
- 評価で「頑張りを認めてもらえた」
- 目標設定で「自分の成長が見えた」
こうした“支援体験”が制度に命を吹き込みます。
④ まとめ|制度と現場の“間”に、支援が必要
制度はつくることが目的ではなく、使われることが目的です。
そして、使われるためには、現場と制度をつなぐ支援の“設計”が必要です。
Live aliveでは、評価制度の設計だけでなく、
運用設計・現場翻訳・面談支援までセットでサポートしています。
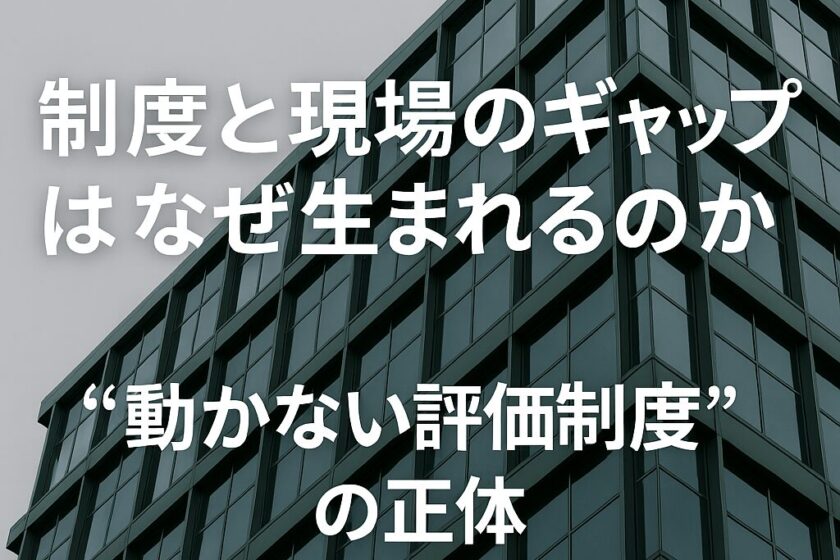
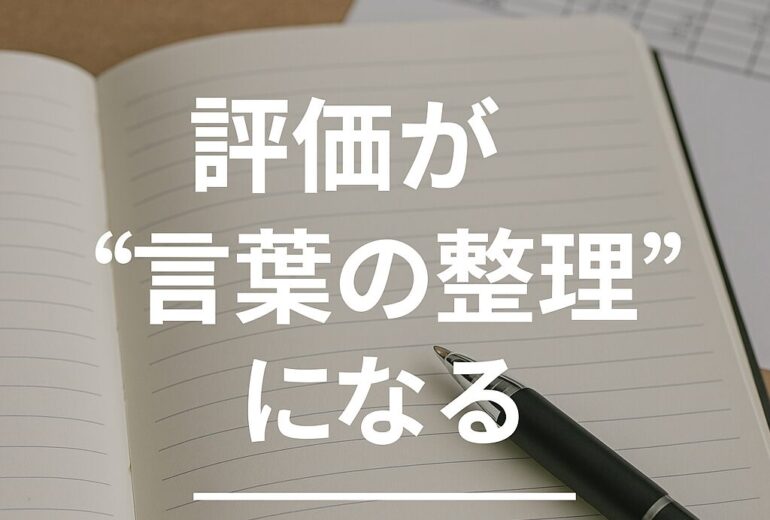
を創る」シリーズ①-10-770x520.jpg)
を創る」シリーズ①-3-770x520.jpg)

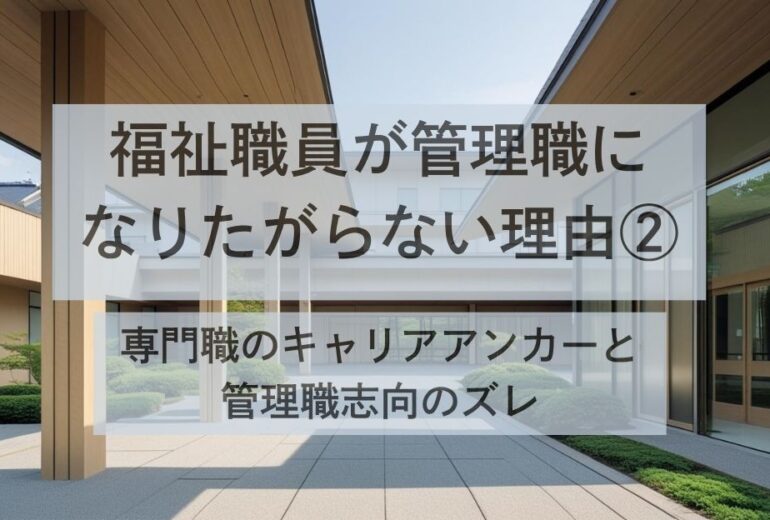

コメント