日本の職場文化には「察して動く」ことが強く求められます。阿吽の呼吸で先回りし、言葉にされない期待を汲み取る。福祉業界はその最たるもので、利用者やご家族の“気持ち”を先に感じ取り、同僚や上司とも言外の合意で仕事を進める傾向が強くあります。
その中で、**「察することが苦手な人」**は、どうしても「なじみにくい社員」と見なされがちです。ですが、これは本当に個人の問題でしょうか? 実は、組織文化そのものがもつ“見えない偏り”に原因が潜んでいます。
組織文化が生む“空気の圧力”
福祉の現場では、
- 空気を読む
- 相手の気持ちを察する
- 和を乱さない
といったスキルが高く評価されます。
そのため、
- 指示待ちに見える
- 行間を読めない
- 言葉での説明を求める
といった人は「向いていない」と早々に烙印を押されやすいのではないでしょうか。
同調圧力がもたらすリスク
「察する力」を重視しすぎると、逆に以下のリスクが生まれます。
- 属人的な判断に依存する → ミスや不公平が温存される
- 言語化が遅れる → 新人が学びにくく、定着率が下がる
- 異質な人材を排除する → 多様性が損なわれる
つまり、「察して動く」文化は強みである一方で、業務や採用の再現性と包摂性を損なう危険もはらんでいます。
“察せない人”が組織にもたらすもの
一見「不器用」な人材も、組織に大きな資源をもたらします。
- 言語化を促す存在
「これってどういう意味ですか?」と聞いてくれる人がいることで、暗黙知が形式知に変わり、マニュアルや教育制度が洗練されます。 - 多様性の担い手
「察する」以外のスキル──論理的整理や専門知識、アイデア発想──で貢献できる場合も多い。 - 組織の鏡
なじめない人がいること自体が、「この組織は誰にとって居心地が良いのか」を映し出す鏡になります。
実践ステップ
暗黙ルールを言葉にする
「察して当然」という前提をやめ、行動指針や期待値を明文化する。これだけで“なじみにくさ”の多くは解消されます。
「察しない力」を役割に転換する
曖昧さに踏み込んで質問できる人は、改善や新人教育の推進役になれる。その特性を役割に結びつけることが重要です。
文化を見直す場をつくる
定期的な対話や研修で「私たちは何を大事にしているか」「その文化は誰かを排除していないか」を点検する。
結論
「察して動けること」が日本社会では高く評価されます。福祉業界は特にその色が濃いため、察せない人は“なじみにくい社員”とされがちです。
ですが、彼らは組織に言語化・多様性・再現性をもたらす重要な存在でもあります。
同調圧力に流されず、察する文化と察しない文化の両方を活かす。
この視点こそが、インクルーシブな組織づくりの第一歩となるでしょう。
を創る」シリーズ①-9-840x560.jpg)
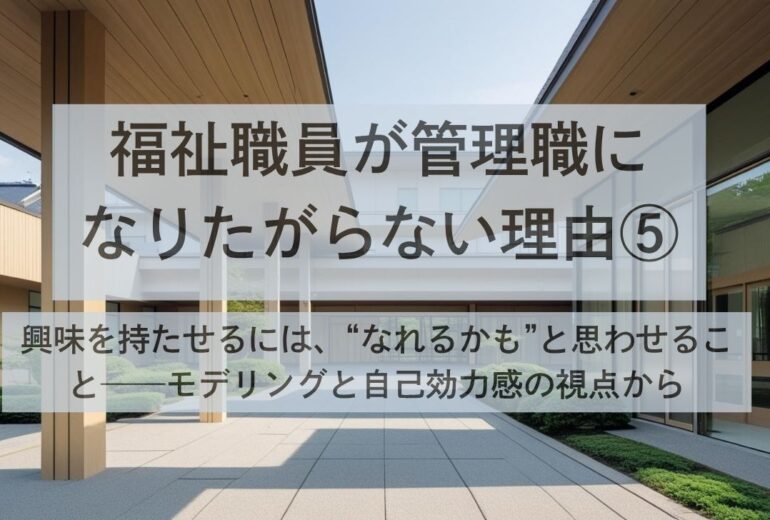
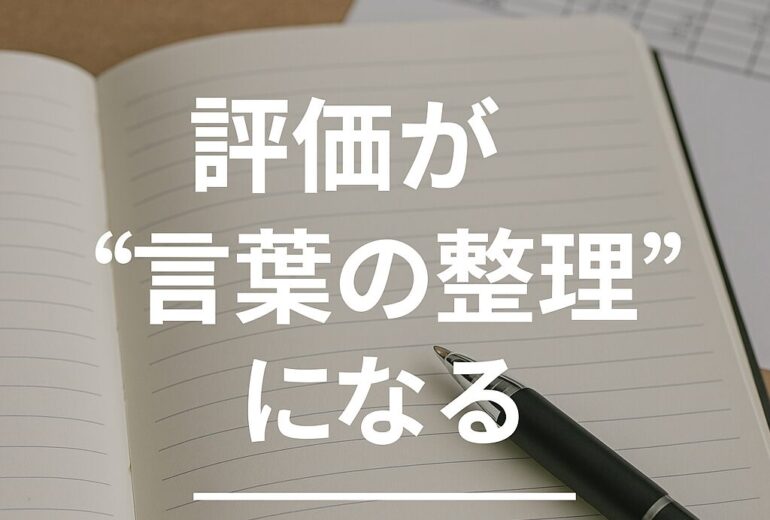
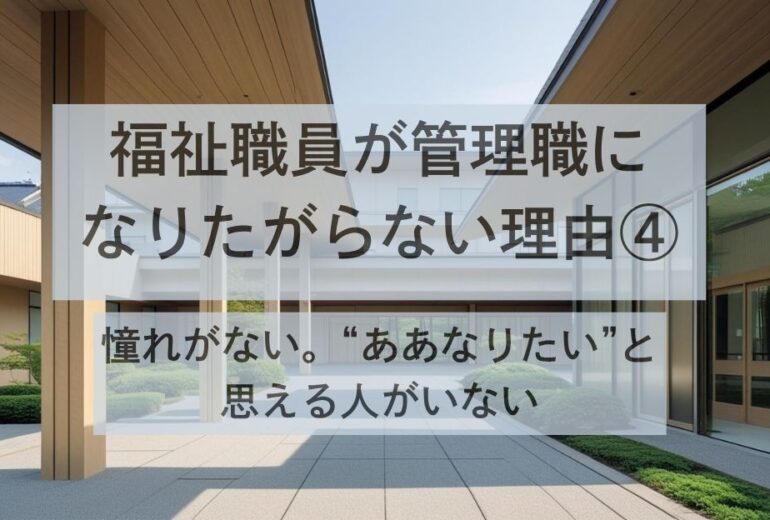
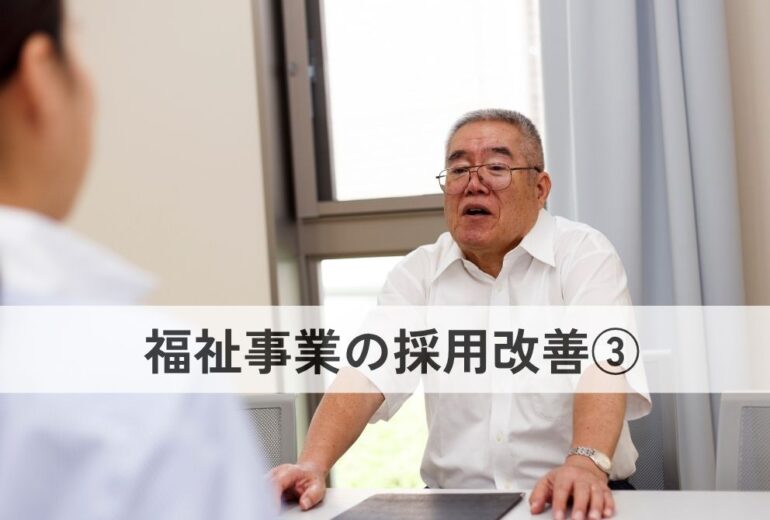

を創る」シリーズ①-4-770x520.jpg)
コメント