福祉業界における評価制度の現状
福祉業界では、いまだに「勤続年数で昇給する給与表」や「形式的な人事考課」が主流です。
その結果、「頑張っても評価されない」「昇給は年功序列で決まっている」といった声が現場から上がり、働き手のモチベーションを下げています。特に若手や中堅層にとっては、自分の努力や成長が正当に評価されないことが、大きな離職理由の一つになっています。
年功序列からの脱却が進みにくい理由
- 公務員制度の影響を受け、給与表が年齢基準で設計されている
- 評価者(管理職)が「人を評価するスキル」を持っていない
- 人事制度そのものを外部の知恵に頼らず、内部で形式的に更新してきた
これらが「評価制度が形骸化する」背景です。
評価制度が離職防止につながるメカニズム
評価制度は単なる査定や給与決定の仕組みではありません。新人や中堅職員の「未来を見せる仕組み」として機能すれば、強力な離職防止装置になります。
モチベーションとキャリアの可視化
「何を達成すれば昇格できるのか」「どのスキルが評価されるのか」が明確であれば、人は成長に向かって努力します。逆に基準が不明確だと、早い段階で「ここにいても成長できない」と感じ、退職を検討しやすくなります。
給与制度との連動で納得感を高める
評価と給与が切り離されていると、「評価されても給料に反映されない」という不満が募ります。評価制度は、給与レンジや昇給ルールと連動して初めて「納得感」を生みます。
新人定着率の改善事例
ある法人では「等級ごとに求められる行動基準」を可視化し、年2回のフィードバックを実施しました。その結果、新卒3年以内の定着率が 60% → 80% に改善した事例があります。
良い評価制度の条件とは?
では、離職を防ぎ、人材が成長できる「良い評価制度」とはどのようなものでしょうか。
基準の明確化と現場への浸透
評価シートをつくって終わりではなく、「現場の職員が自分で読んで理解できること」が最低条件です。
専門職キャリアと管理職キャリアの両立
福祉業界では「管理職になりたくない」専門職が多く存在します。評価制度は「専門職としてのキャリア」と「管理職としてのキャリア」の両方を設計することが必須です。
フィードバック文化の定着
評価は年1回の人事考課ではなく、日常の対話を通じたフィードバックで機能します。「評価シート」と「コミュニケーション」の両輪で仕組みを回すことが重要です。
制度設計は“外部の知恵”を取り入れるべき
評価制度を内部で完結させると「現状追認」に陥りやすくなります。
経営陣だけでは限界がある理由
- 現場のリアルと乖離した評価基準になりがち
- 人間関係やしがらみで「本当に必要な改革」ができない
第三者視点での公平性と実効性
外部の専門家を入れることで、制度が客観性を持ち、現場に浸透しやすくなります。実際に導入を支援した法人でも「外部の設計が入ったことで、幹部間の合意形成がスムーズになった」という声が多く聞かれます。
まとめ──評価制度は「離職予防装置」である
新人の離職理由を突き詰めると「評価されない」「未来が見えない」が必ず出てきます。逆に言えば、評価制度は “給与表以上の意味を持つ、離職予防装置” と言えます。
これからの福祉法人に求められるのは、単なる給与表の見直しではなく「評価制度を通じてキャリアの未来を示すこと」です。
評価制度設計に関するお問合せ
Live alive株式会社では、福祉事業として丁寧につくられてきた皆さんの会社の良さを残しながら、新しい組織・制度を設計していくお手伝いをしています。お問合せはこちらまで。
を創る」シリーズ①-4-840x560.jpg)
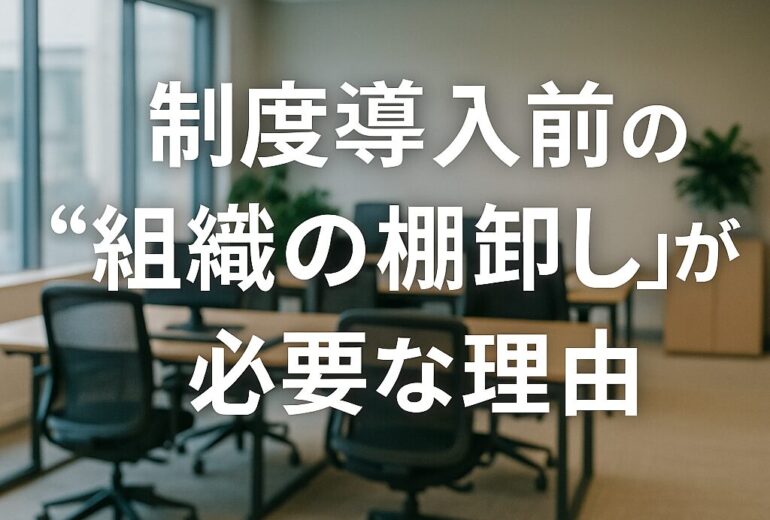
を創る」シリーズ①-3-770x520.jpg)
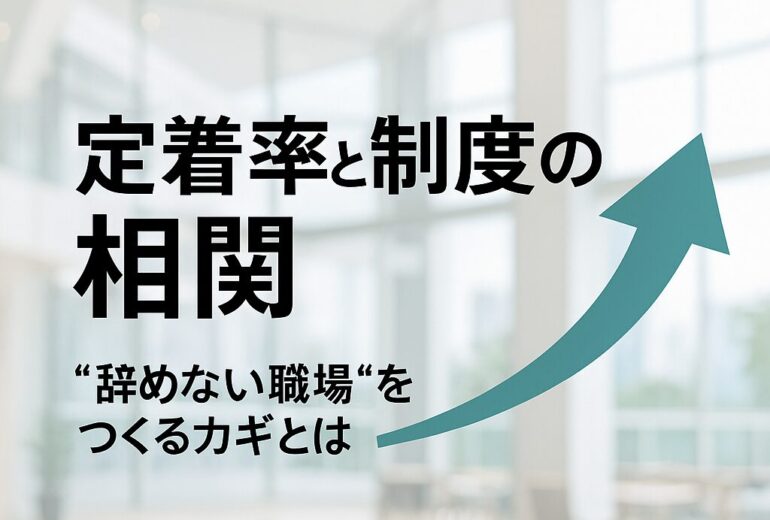
を創る」シリーズ①-2-770x520.jpg)
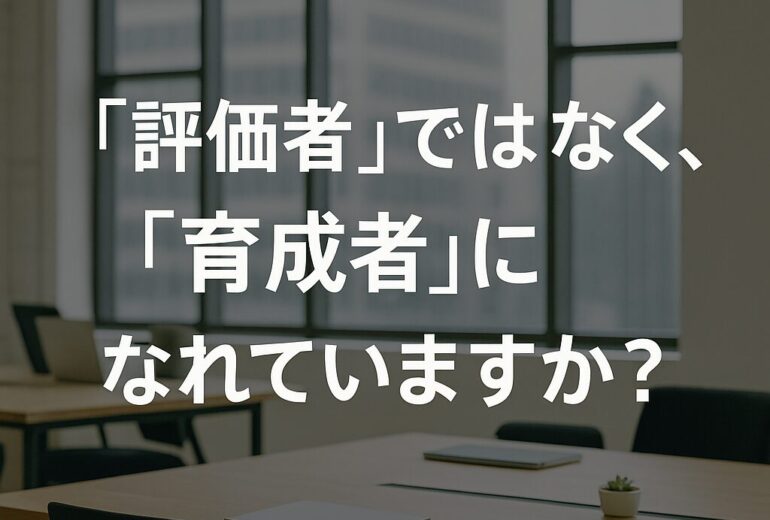
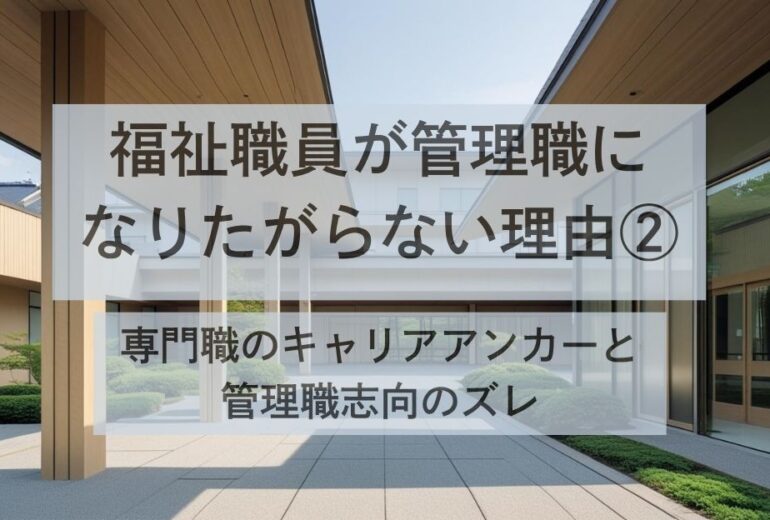
コメント