福祉業界での離職は、「辞めたい」という言葉が出た時点で、すでに引き止めが難しいことが多いです。
実は、離職には必ず“予兆”があります。それを早期に掴めれば、まだ防げるケースが少なくありません。
近年では、AIやHRテックの進化により、この予兆=シグナルを数値として捉えることが可能になってきました。
今回は、福祉現場で特によく見られる3つの離職予測シグナルと、その対策をご紹介します。
① コミュニケーションの減少
- 現象例:挨拶や雑談が減る/業務連絡が端的・最小限になる
- リスク:心理的距離の拡大、孤立感の増加
- 対策:
- 月1回の1on1面談を必ず実施
- ペアワークの頻度を意図的に増やす(新人だけでなくベテラン同士も)
- オンラインチャットや掲示板で日常の雑談スペースを作る
② 自己効力感の低下
- 現象例:「どうせ意見を言っても変わらない」と感じる/称賛や成果の共有が減る
- リスク:業務モチベーションの低下、挑戦回避行動の増加
- 対策:
- 小さな成功体験を全体会議や掲示板で共有
- 進捗状況を上司が週単位でフィードバック
- 職員からの提案をすぐに小規模でも試してみる「即試し文化」
③ 組織への関与度の低下
- 現象例:研修・イベント・委員会活動などへの参加率が低下
- リスク:組織への帰属意識の薄れ、関係の希薄化
- 対策:
- 新しい役割のアサイン(委員会や小規模プロジェクトなど)
- 越境的な学び(外部研修、他法人との交流研修)を提供
- イベントや研修の設計を「楽しい」「学べる」「人とつながれる」の三拍子で再構築
科学的根拠(エビデンス)
- ギャラップのエンゲージメント調査では、従業員の関与度低下は離職意向の高まりと強く相関
- Job Demands-Resources モデル(要求と資源のバランス)では、心理的資源(評価・支援)が不足するとストレス増加と離職リスク上昇につながることが示されている
実践ステップ
- 離職予測KPIを設定(例:1on1実施率、イベント参加率、雑談発言数など)
- データ収集と可視化(紙やExcelでもOK)
- PDCAを回す(改善策の小規模実験→効果測定→次策)
- 属人的な「なんとなく察する」から、定量的な判断へシフト
を創る」シリーズ①-2-1-840x560.jpg)
を創る」シリーズ①-770x520.jpg)

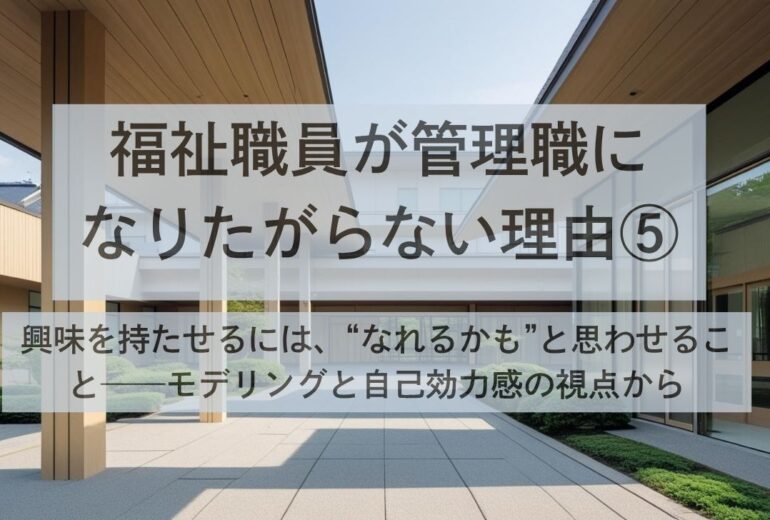
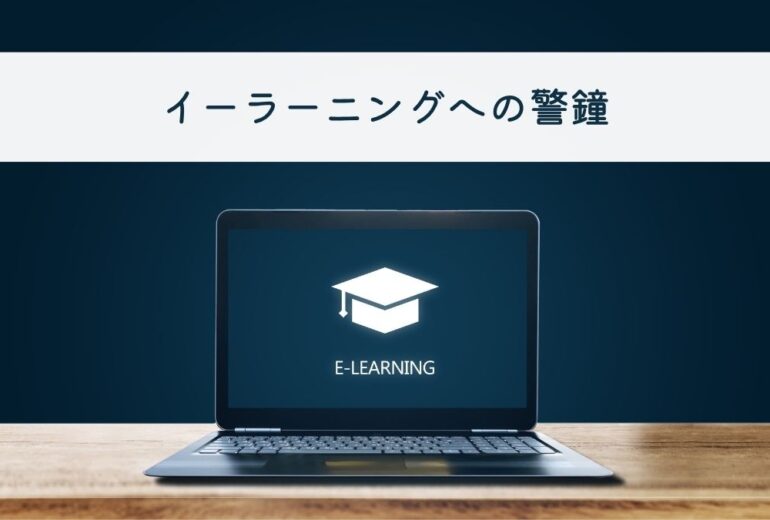
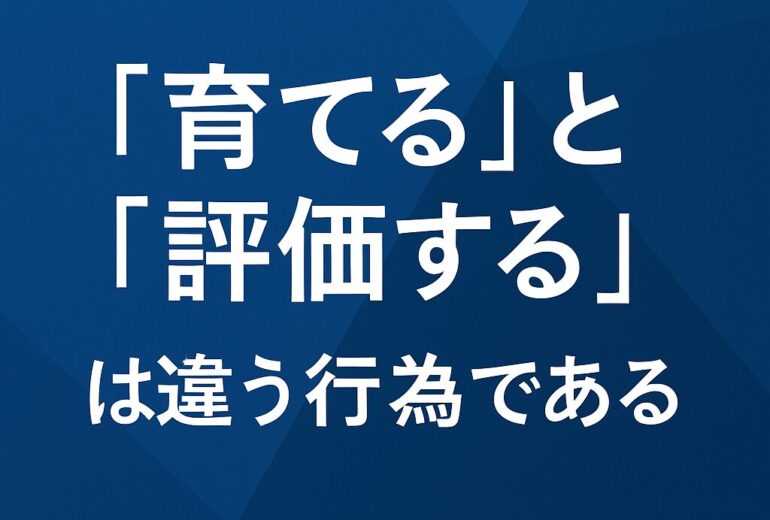
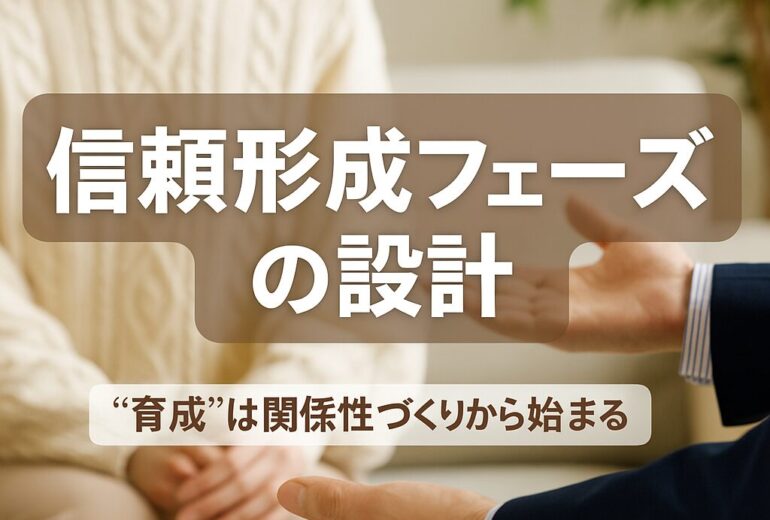
コメント