「“経営の壁”ではなく“学びの壁”が若手を遠ざける」――問われているのは、若手ではなく“上の学び直し”
「若手の意見も聞こう」「対話の場を設けよう」
そうして始まったプロジェクトが、いつのまにか経営からの一方的な指導に変わっていく――そんな場面を見たことはありませんか?
最初は「フラットな関係で進めよう」としていたのに、若手が経営課題を指摘し始めると、雲行きが怪しくなる。
「そんなに言うなら、まずお前らがやることやれよ」という空気が生まれ、最後は「今の若い世代は……」と“世代のせい”にしてしまう。
これは“経営の壁”ではなく、学びの壁です。
■ 組織が学ぶとは、立場の強い人が「分からない」と言えること
若手職員に「学んでほしい」「自走してほしい」と言うなら、
まず経営層や年長管理職が、学び手としての姿勢を見せる必要があります。
アージリスの「シングル・ループ学習/ダブル・ループ学習」で言えば、
若手にばかり学習を求める組織は、自分たちの“前提”を問わない=シングルループにとどまっていると言えます。
■ 若手からの提案は、信頼の証である
若手が経営の課題を指摘するのは、組織をより良くしたいという意思の現れです。
それを“生意気”と感じて跳ね返してしまうと、学ぶ組織の芽はそこで途絶えます。
むしろ、経営層はこう返すべきです。
「確かに、それは自分たちも課題だと思っている」
「一緒にどうしたらいいか考えさせてほしい」
この言葉が言えるかどうかが、“学びの壁”を越えるか否かの分かれ道です。
■ 経営は、答えを持つ人ではなく、「問いを持ち続ける人」であるべき
経営層・年長者が「正解を教える役」になってしまうと、
若手は自分の考えを持つことができなくなります。
いま必要なのは、**答えを示すリーダーではなく、「問いを持ち続けるリーダー」**です。
「自分にも分からないことがある」と言える勇気こそが、若手に学ぶ余白を与えるのです。
■ 次回予告
次回は、経営層・年長者が“学びのトップランナー”になるために必要なことを掘り下げます。
特に、経営層・管理職層・中高年にとって「学び直し=リスキリング」がなぜ難しいのか?というテーマを扱います。
✒️Live alive株式会社では、福祉法人向けに「若手との対話設計」「管理職の学び直し支援」「越境型研修」などのプログラムもご用意しています。
お気軽にご相談ください。
を創る」シリーズ①-4-840x560.jpg)

を創る」シリーズ①-2-770x520.jpg)
を創る」シリーズ①-3-770x520.jpg)

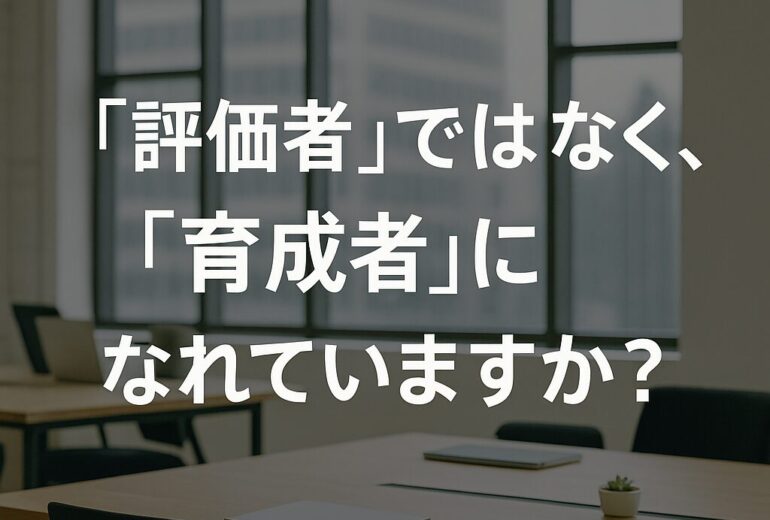
を創る」シリーズ①-6-770x520.jpg)
コメント