■ 導入:なぜ今、イーラーニングが選ばれるのか?
「職員の学びの機会は必要だ」
「人材が辞めない組織にしたい」
そんな思いから、イーラーニングを導入する福祉法人が増えています。
動画研修やオンデマンド学習は、職員が自分のペースで学べる手軽な仕組みとして重宝されがちです。また、国保連の請求管理システムなどのオプションとして販売されているため、手軽に購入できることも、この状況が増えている理由ではあります。
もちろんこれは悪いことではありません。
最低限の知識を全職員に届けるという意味では、有効な手段です。
しかし、実際に現場でこうした声も聞かれます:
- 「見たけど、現場でどう活かせばいいのか分からない」
- 「視聴が義務になっているだけで、学びにはなっていない」
- 「一人で見て終わるから、誰とも話せないし記憶に残らない」
加えて、法人側にもこんな本音があることが見て取れます。
「一括契約すれば、人材育成の体裁が整う」
「視聴ログで“教育しました”と報告できる」
「多忙な中でも、最低限やった感が出せる」
つまり、“楽に人材育成を済ませたい”という期待が、イーラーニングを選ぶもう一つの背景にあるようにも思います。
■ イーラーニングの“限界”とは?
イーラーニングには、以下のような構造的な弱点があります。
・学びが孤立する
一人で動画を見る形式では、職場内での対話が生まれず、同僚性や共有知が育ちません。
・身体知・実践知が育たない
知識は得られても、動作・振る舞い・感情調整といった現場に必要なスキルは身につきにくい。
・行動変容が起きにくい
視聴で終わると「学んだ気にはなる」が、行動を変えるところまでいかない。
・学びの連鎖が生まれない
学んだことを誰かに伝える、話す、フィードバックをもらうといった再生産の仕組みが欠落。
■ 理論で見る「なぜ複合的な学びが必要か」
🔸ダブルループ学習(アージリス)
シングルループ=行動の修正
ダブルループ=前提・価値観そのものの再構築
→ 一人の視聴では、前提が問われる機会がない
🔸経験学習モデル(コルブ)
経験→内省→概念化→実践
→ イーラーニングは“概念化”偏重。経験・内省が抜け落ちる
🔸ピアラーニング・越境学習
他者との関わりの中で、知識が実感をともなって定着
→ 職場内・法人間での学びの循環がカギ
■ 「学びを文化にする」ために法人ができること
✅ Step1:共有の場をつくる
- 動画視聴後、ペアやチームで5分でも対話
- 見た内容を社内のグループウェアなどで投稿共有
✅ Step2:現場に“実践する時間”を意図的に埋め込む
- 管理職が「見てどう思った?やってみようか?」と促す
- ちょっとしたフィードバックの時間を設ける
✅ Step3:越境と循環を起こす
- 他施設との学び合い(オンライン勉強会・交流会)
- 学びの“実践報告”を共有するカルチャー醸成
■ 最後に:経営に問いたいこと
制度を入れたことで安心していないか?
視聴記録や受講率だけで満足していないか?
あなた自身が最近、何を学び、誰と共有しましたか?
学びは、文化になって初めて“人を辞めさせない”力になるのです。
✒️Live alive株式会社では
イーラーニングを“つなげる”学習設計・ピア支援・越境学習など、
知識を実践につなげる仕掛けの導入をサポートしています。
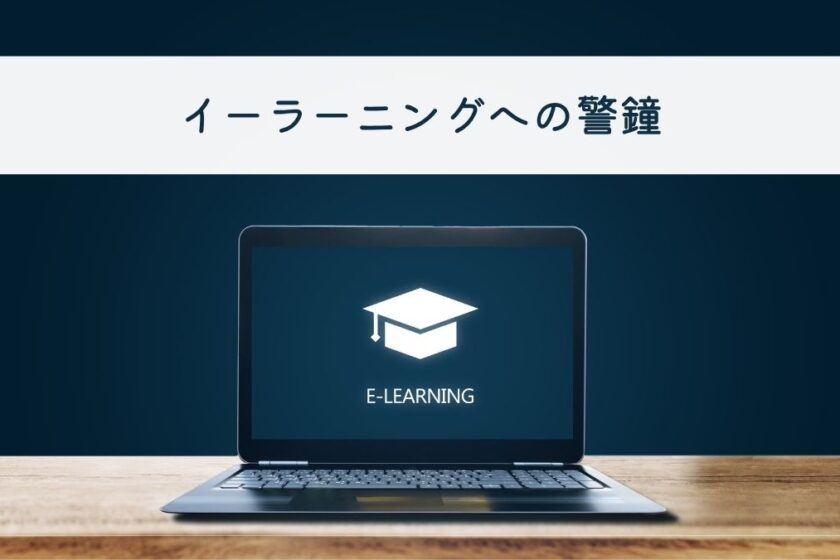
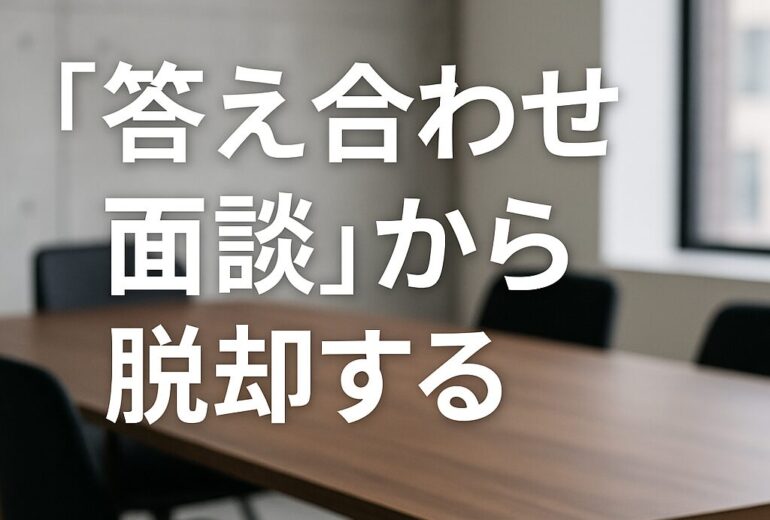

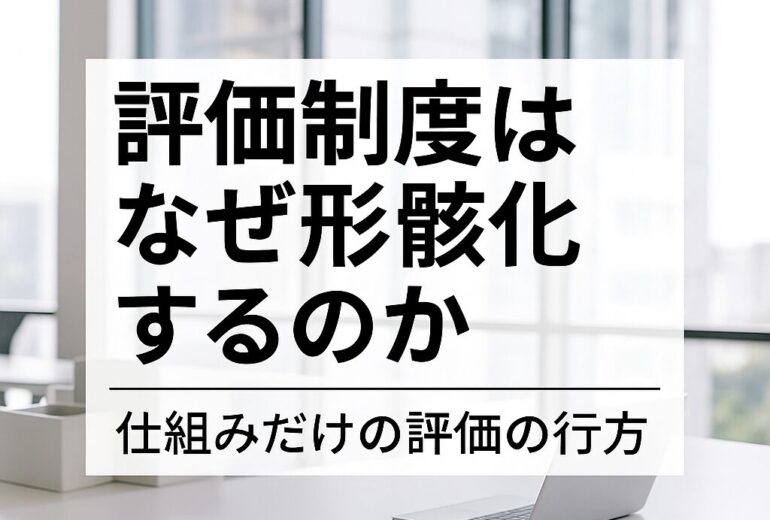
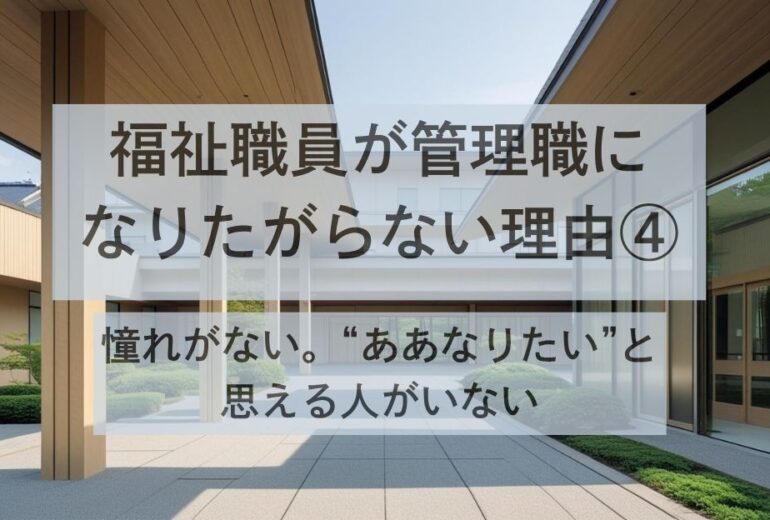

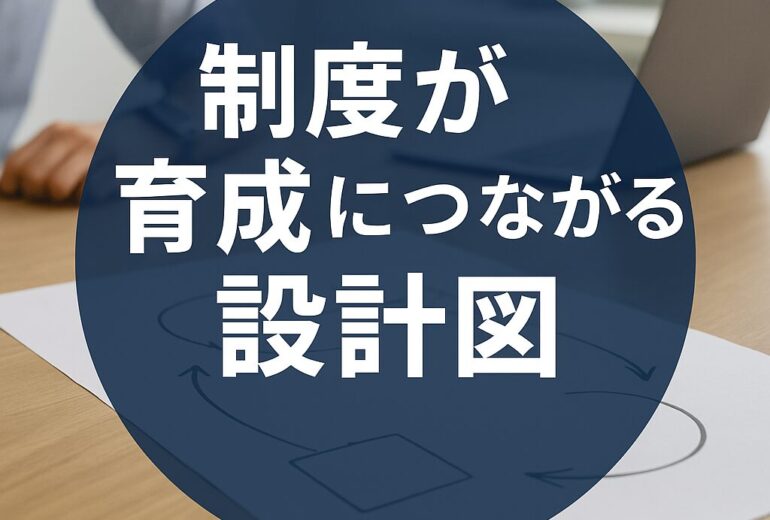
コメント