① 導入|「制度はある。でも辞める」現場の声から
前回の記事で、福祉業界の離職率の高さとその背景について触れました。
「評価制度もあるし、マニュアルも整備してるのに、職員が辞めてしまう」という法人があります。その原因の一つは、“制度が機能していない”こと。つまり、作った制度が、職員の育成や定着にきちんとつながっていないという現実です。
② 本題|評価制度を「機能させる」3つのコツ
制度を“入れる”だけでは意味がありません。
制度を“使える”ものにし、“職員の成長”や“現場の対話”とつなげる必要があります。
1|目的を「評価」から「対話」にシフトする
評価制度は点数をつけるための道具ではありません。
本質は、“職員がどこに向かうべきかを共有する”対話の場づくりです。
だからこそ、評価制度を回すには、上司と部下の面談の質が鍵になります。
面談=業務報告の場 ではなく、
面談=価値観と方向性をすり合わせる場 に。
2|「簡単」で「続く」仕組みにする
良い制度でも、複雑すぎて運用できなければ意味がありません。
福祉現場では、シンプルさと時間効率が何より重要です。
- 目標項目は1つ~3つ以内に絞る
- 施設利用者様向けの相談援助と評価者研修を抱き合わせて行い、評価者の面談力を少しずつ上げていく
というように、「これならやれる」という制度設計がカギになります。
3|“育成”とつなげることで意味が出る
評価制度が評価だけで終わると、職員は「結局、自分の給料や立場には影響ない」と感じてしまいます。
だからこそ、評価→育成→面談→目標→自己効力感の循環が大切です。
Live aliveでは、キャリア支援シートや月次面談テンプレートをセットで整えることで、制度と人材育成を結びつける支援をしています。
③ まとめ|制度は「育つ組織」をつくるための道具
評価制度は、整えて終わりではなく、活かされて初めて価値を持ちます。
- 面談文化をつくること
- 現場が使い続けられること
- 職員が“見てもらえている”と感じること
この3つを仕組みとして整えたとき、はじめて制度は“辞めない職場づくり”に貢献します。
制度を入れた“その後”が不安な法人様へ
Live aliveでは、評価制度の「設計」だけでなく、「現場に根づく運用支援」まで伴走しています。
制度があるのに辞める。そんな現場に心当たりのある方、まずは“制度の見直し”から一緒に始めてみませんか?
▶ お問い合わせはこちら:https://live-alive.jp
▶ 月額5万円からのライトプランもございます


を創る」シリーズ①-8-770x520.jpg)
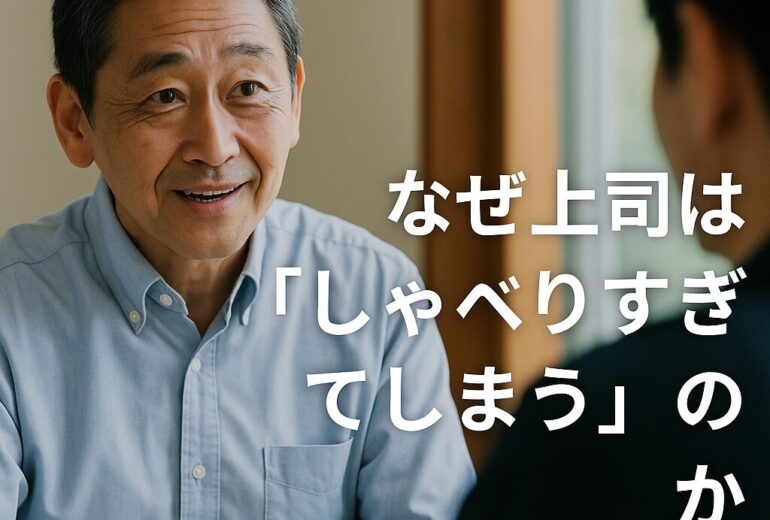
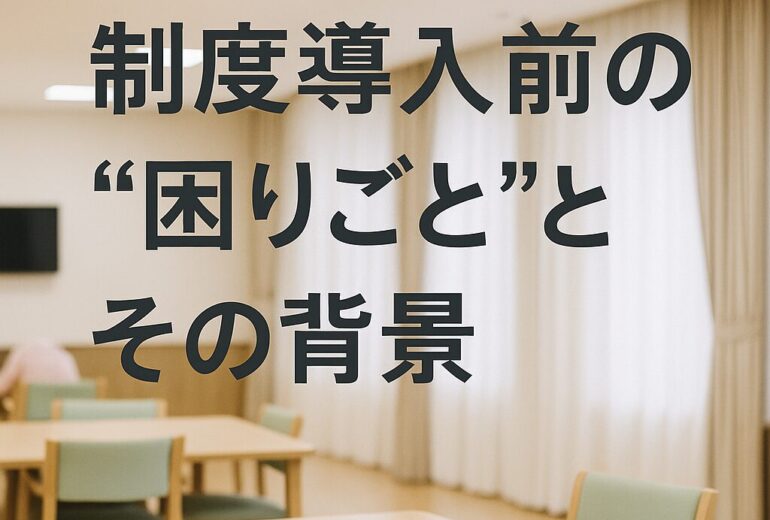


コメント